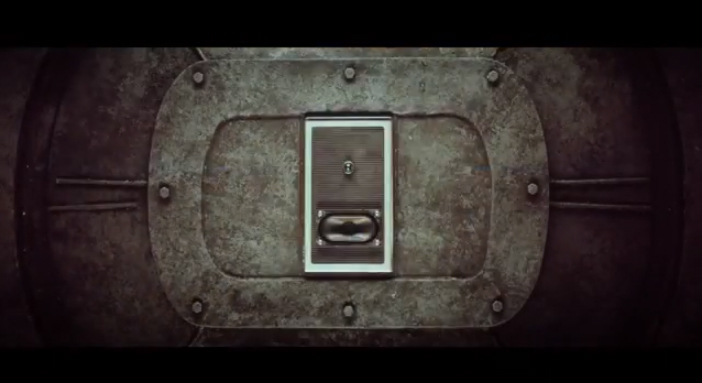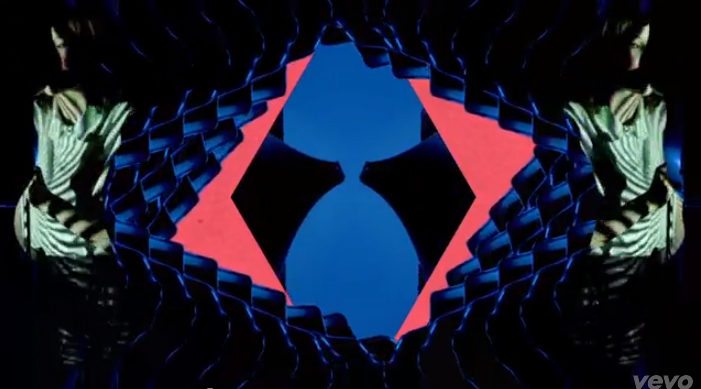Special
CHVRCHES 『ザ・ボーンズ・オブ・ワット・ユー・ビリーヴ』インタビュー

ローレン・メイベリー、イアン・クック、マーティン・ドハーティによって2011年に英・グラスゴーにて結成された3人組エレクトロ・ポップ・バンド、CHVRCHES(チャーチズ)。【BBC Sound of 2013】では5位、SXSWでのライブをはじめ単独アメリカ・ツアーも軒並みソールド・アウトとなり、最近ではデペッシュ・モードのヨーロッパ・ツアーのオープニング・アクトに抜擢されるなど各国で旋風を巻き起こしている彼ら。その人気はここ日本でも加熱しており、7月にリリースされた日本独自の企画盤『EP』も大ヒットとなった。【SUMMER SONIC 2013】に出演する為に、8月に初来日を果たしたチャーチズのマーティン・ドハーティが、9月25日にリリースされるデビュー・アルバム『ザ・ボーンズ・オブ・ワット・ユー・ビリーヴ』を中心に語ってくれた。
【SUMMER SONIC 2013】CHVRCHESライブ・レポート>> CLICK HERE!
このバンドが魅力的だと感じたのは、3人が集まると、
いとも簡単に曲が作れたからだった
――初めての日本はいかがですか?
マーティン・ドハーティ:昨日はご飯を食べに行って、渋谷の街に繰り出したよ。それから夜遅くまで卓球をしてた。僕らとバンドのクルーでよく対決してるんだ!
――念願の猫カフェには?
マーティン:昨日行ってみたんだけど、残念ながら閉まってたんだ。ローレンがすごく行きたがってるから、今夜また行ってみるみたい。僕らは屋上でサッカーをするんだ。僕にしてみれば、すごくクレイジーなことだよ、ビルの屋上でサッカーなんて!それにとにかく暑いね~。今日はまだ15分ぐらいしか外に出てないけど。
――明日【SUMMER SONIC】で出演するステージは屋内なので、そこまで暑くはないかな、と思いますよ(笑)。
マーティン:良かった~。日本に来る前に、ヨーロッパでいくつかライブをやったんだけど、フランスの会場は屋根がない円形演技場で、サウンドチェックが終わってから機材をそのままにしていたら、暑さでキーボードの一部が溶けちゃったんだ(笑)。
――(笑)。ではインタビューに。まずはチャーチズがどのような経緯で結成されたのか教えてください。3人とも以前は他のバンドに所属していたそうですね。
マーティン:僕はセッション・キーボディストとして活動してた。
――ザ・トワイライト・サッドの。
マーティン:そう。ツアー三昧で、色々な国に行くことができたけれど、毎晩ステージに上がって他人が作った曲を演奏することに満足できなくなったんだ。何かバンドにとっていい出来事が起って、同じようにその場にいても、自分のことではないような疎外感がどうしてもあった。自分で音楽を作ろうと思うようになったのは、それが一番大きな理由。そこで僕と似た境遇で音楽活動をしていたイアンに相談した。「何かやろう」と2人で何年間も話し合ってきたけれど、なかなか行動に移せなくて、ある日やっと「やるぞ!」って決心して、チャーチズをスタートさせたんだ。ローレンが参加したのはその直後。後はトントン拍子で1年半後には東京にいる(笑)!信じられないね。まったく予想していなかった…というかこんなこと予想なんてできないよね。

▲ 「The Mother We Share」 (Official Video)
――チャーチズ以前は、メンバー全員まったくサウンドが異なるバンドに所属していましたが、主にシンセサイザーやキーボードを軸とした現在の音楽性はどのように定められたのですか?
マーティン:僕の観点からすると必然的なことだった。元々キーボード・プレーヤーだったし、ギター・バンドに所属していてもシンセサイザーやラップトップでの演奏を担当していたから。今チャーチズとして作っている音楽は、僕がこれまで聴いてきた音楽に影響されている。現代のエレクトロニック・ミュージックやラップ、90年代~2000年代初期のR&Bミュージックにもとても興味があって、それをフュージョンするとチャーチズの音楽性に違和感なく到達する。全然違うタイプのバンドに所属していたイアンもローレンも80年代の音楽は昔から好きだったので、それがこのバンドの中立の場となってる。総体的には大きな変化に見えるかもしれないけれど、僕にとっては自然な流れだった。サウンドを影響している要因はもう1点あって、僕らはイアンのとても小さなプロジェクト・スタジオで作業している。キーボードやドラム・マシーンは山ほどあるけれど、ライブ・ルームがないから、“ちゃんとした”バンド編成にしようとしても、それが物理的に無理なんだ。リハーサル・スタジオを借りるにはお金がかかるし…それに今まで他のバンドに所属していた経験から言って、ドラマーがいると厄介だから、出来ればいない方がいいな、なんて思って(笑)。
――初めて3人で曲づくりを行った際のバンドのケミストリーというのは?
マーティン:驚くぐらいに良かったんだ!当初このバンドが魅力的だと感じたのは、3人が集まると、いとも簡単に曲が作れたからだった。その部分にメンバー全員がエキサイトして、時間と労力をつぎ込み、活動を本格化する原動力にもなった。通常、初めてバンドとして曲を作るには少し時間を要するけれど、最初に数曲作った時点で、僕が今までに経験した事がないようなスピードで、曲のベースとなるリズムやメロディが次々と出来上がっていった。それはローレンとイアンも感じたことで、新たに曲を作るごとに、より一貫していった。
――最初から、そこまで相性がいいバンドはなかなか珍しいですよね。
マーティン:そう、とても自然な成り行きで、困難だと感じたことはまったくなかった。すごく不思議だけど、ラッキーな偶然が重なったんだと思う。一番最初にバンドとして曲づくりを行ったのは2011年の後半で、初めて曲をリリースしたのが2012年の5月だから、普通では考えられないようなスピードだよね。
リリース情報
関連リンク
2人のプロデューサーとそのはけ口である
単なる女の子という風に捉えられないように

▲ 「We Sink」 (Session for BBC Radio 1)
――そして待望のデビュー・アルバム『ザ・ボーンズ・オブ・ワット・ユー・ビリーヴ』が日本で9月25日にリリースされますね。まず最初に、“音オタク”のマーティンがアルバムの中で一番気に入っているシークエンスや曲を教えてください。
マーティン:(笑)。総体的には、ダークな部分が好きだね。一番好きな曲は、アルバム2曲目の「We Sink」。なぜかと言うと、僕らがこのアルバムで目指したことを完璧に具現化できた曲だと思うから。プロダクションを極限までにアグレッシヴにして、それをローレンの無垢でスウィートなヴォーカルで中和させ、バランスをとる。曲の最初から最後まで使われているアープ・サウンドがあるんだけど、それをソロで聴くと不快でゆがんだ…わざとラフで乱雑にしていて、同じようにドラム・ビートもギリギリまでプッシュして、ローレンのヴォーカル・レイヤーが入った瞬間にそれが中和されるように構成されている。実はこれはアルバムに収録されている他の曲でも試みたことだけど、この曲が僕が構想していたものに一番近い出来だと思う。
――マーティン、そしてイアンもプロデューサーとしての過去がありますが、あえてセルフ・プロデュースにこだわったのは?
マーティン:各国で違うレーベルに所属しているけれど、それは僕らがどのようなバンドかを理解してくれたレーベルと契約したからで、デビュー・アルバムに関しても自分たちですべてのプロセスを担いたかったからなんだ。だって「デモはいいね。じゃあ、この金額を上げるから、この有名なプロデューサーを起用したらいいんじゃない」、なんていうレーベルは僕らの理にかなってないから。でも最終的にミックスは他の人に頼んだ。本当は自分たちだけの力で完成させたかったけど、13か月かけてずっと作り続けてきたから、作品との距離が近くなりすぎて、的確な判断ができるかわからなかったんだ。そこで僕が知ってる最高に素晴らしいアメリカ人ミックス・エンジニアのリッチ・コスティの元へ音源を送った。彼はロック系のアルバムを多く手掛けていて、僕らがどのような作品にしたかったかを理解してくれたから、きちんと最後まで見届けてくれると確信していた。クリーンなプロダクションではなく、ラフで、生々しくて、リアルな感じにね。
――作詞は、主にローレンが担当しているとのことですが、具体的な曲づくりのプロセスについて教えてください。
マーティン:このバンドはメンバー全員が平等で、アイディアが気に入らなかったら却下する権利も持ってる(笑)。でもそれって3人だから成立するのかもしれないね。基本として、インスピレーションがあって、そこからみんなで曲を作り上げていくという感じで、誰かが「この曲作ったんだ」とスタジオにフル・ソングを持ちいることは絶対にない。すべてのセッションは、パソコンの真っ白なスクリーンからスタートする。多くの場合、最初のサウンドはシンセサイザーかドラムのビートから生まれて、それが面白いサウンドだとしたら、そこから20~30分間が曲にとってのキー・ポイントとなる。アイディアが次々と生まれ、ヘッドフォンをつけて適当に歌い続けると、曲のコアとなるものが自然と出来上がるんだ。
――メロディ?
マーティン:うん、ほとんどの場合そうだね。そこから曲に成長させて、詞を書いていくんだ。

Photo: (C)SUMMER SONIC 2013 All Rights Reserved.
――アルバムには「You Caught The Light」「Under The Tide」など、マーティンがヴォーカルを担当している曲もいくつか収録されていますよね。
マーティン:僕がメロディを思いついたからと言って、曲に対して所有権があるわけではなくて、単純に曲に合ったヴォーカリストを選んでる。元々のデモで僕が歌っていた場合もあるし、特定のキーの曲だとローレンのヴォーカルだと「最悪!」ってこともある(笑)。思考錯誤を重ね、曲に合った“声”を当てはめていく。僕が歌っている曲は、デモ・バージョンから歌ってきていたものが大半で、それが一番しっくりきたから、そのままアルバムでもヴォーカルを担当している。
それとアルバムを通して聴くにはヴァラエティや変化が必要だと感じていて、“声”もバンドのサウンドのひとつで、器具だと考えているんだ。最近だとシングルをダウンロードして、音楽を消費する行為がポピュラーになりつつあるけれど、僕らはアルバムを通して聴くという行為を重んじている。だからローレンがヴォーカルの曲があるように、男性ヴォーカルの曲もアルバムの流れの中において不可欠なものなんだ。
――話を聞いていると、バンドとしての揺るぎないスタンスや想いがひしひしと伝わってきますが、ローレンがフロントウーマンとしてアイドル視されているのには正直違和感を感じますか?
マーティン:2人の男性と女性がいるバンド…とくにトライアングルになっているほど、プレスや音楽評論家は、女性をセンターにしたがる傾向がある。特にその子が可愛いくて、いい声をしていると、それだけで創作過程に携わってないと思われてしまうことが多い。それってすごくセクシストで差別的な考え方だよね。僕らは、バンドのメンバーとして彼女が曲づくりに不可欠だということを知っているし、逆にライブにおいては、ステージ上のエネルギーを保つ上で、僕ら2人の男性メンバーも大きく貢献していると思っている。今はそうでもないけれど、バンドを結成した当初、このステレオタイプに対する施策についてよく話し合ったんだ。2人のプロデューサーとそのはけ口である単なる女の子という風に捉えられないように。たとえばユーリズミックスだと、デイヴ・スチュワートが“ブレーン”でアニー・レノックスが“声”というイメージが定着してしまって、結局上手くいかなかった。後はヤズーのヴィンス・クラークとアリソン・モイエ…もう何十年前から続いている問題だと思うな。そういったステレオタイプにはめ込むのが、一番簡単にバンドを差別化する方法だというもの理解もできるけどね。
リリース情報
関連リンク
ライブというのはステージ上で楽曲を生で演奏する、
ということにしか結びつかない

▲ 「Now is Not The Time」 (Live)
――既にアルバムから何曲かライブで披露していますが、曲をライブで演奏する時に心掛けたことは?特にエレクトロニック・アーティストの場合は、通常のバンドに比べ、生で演奏可能な部分が制限されますし、たとえばアルバムのラストに収録されている「You Caught The Light」なんかは、不可能に近そうですよね。
マーティン:確かに!あの曲は一生ライブでやらないかも(笑)。ギター、ベース、リヴァ―ヴ…色々細かい要素が多すぎるからね。チャーチズにとって重要なのは、ステージであてぶりをするのではなく、きちんと“ライブ”で演奏するということ。なぜかと言うと、最近そういう類のエレクトロニック・アーティストが増えてきているから。それに対してとやかく言うつもりはない…観客からチケット代をもらって、大げさにフェーダーから手を放すアクションをするのがクールだと思っているんだったら、それはそれでいいと思う。でも僕にとってそんなの全然面白くないし、“生”の音楽が生み出すエネルギーとは全く違う。結成前から全員ライブ・バンドに所属していたから、逆に言えばライブというのはステージ上で楽曲を生で演奏する、ということにしか結びつかない。だからアルバムで使用したキーボードは、ほとんどステージで使っているよ。ドラムはコンピューターを使っているのと再現不可能なクレイジーなサンプル以外は、すべて僕とイアンが生で演奏し、コントロールしている。でもきちんと正確に演奏できるようになるまで時間がかかったし、チャレンジだったね。
――最近ではデペッシュ・モードのヨーロッパ・ツアーのオープニング・アクトを務めたり、多くの音楽フェスティヴァルにも出演していますが、バンドの人気が高まったな、と感じた瞬間はありましたか?
マーティン:あまり自分たちのまわりで起こっていることを完璧に理解しようとは思っていなんだ。今年はここに行って、これをして、なんて考え始めるとキリがないし、うぬぼれることは簡単だから。あえて言えば、デペッシュ・モードのオープニング・アクトとして、ミラノの有名なサッカー・スタジアム、サン・シーロで演奏できたのは最高だった。サッカーファンなら誰でも知っているスタジアムで、僕はサッカーが大好きだから「スゲー!」って演奏中ずっと思ってた(笑)。チャーチズ以前の音楽活動期間を含めると、かなり長い間ライブをしてきたけれど、こんな場所で演奏できるなんて、メンバー全員思ってもいなかったから。

Photo: (C)SUMMER SONIC 2013 All Rights Reserved.
――それにバンド結成から1年半足らずで、地元グラスゴーの大型音楽フェスティヴァル【ティー・イン・ザ・パーク】にも出演できたのは、いい凱旋ライブになったのでは?
マーティン:そうだね!すごくクールだった。でも実は知っている人が多い方がハードだよ…。イギリスやスコットランドで3~4千人の観客を前にするより、イタリアで5万人に演奏する方が気楽なんだ。知り合いが多いと、演奏中に目があったのが、自分の好きな人だったらいいけど、お互い嫌いな人だったら、「あいつ僕らが失敗するのを待ってるんだな。」とか、余計なこと考え始めてちゃって、演奏に集中できなくなってしまう。だから意外とスコットランドでのショーの方が難しいんだよ。今後スコットランドでいくつかライブを控えてるんだけど、どうなるか、神のみぞ知るって感じだね(笑)。
――もしチャーチズが音楽フェスをキュレートをするとしたら、どこで行い、どのようなラインナップにしますか?ちなみにプリンスは出演するんですよね(笑)。
マーティン:いや、僕だったらプリンスをラインナップから外して、マイケル・ジャクソンに出演してもらう!よくプリンスのことを訊かれるけど、好きなのはローレンで、僕は断然マイケル・ジャクソン派なんだ(笑)。80年代でもそうだったと思うけど、僕からしてみれば、プリンスとマイケル・ジャクソンが両方好きなんてありえなくて、2人は絶対相容れない。場所はどこかな~?多分日本だね。この10年間で色々な国をツアーしているけれど、今回の初来日には、10年前に初めてニューヨークに行った時と同じぐらい圧倒された。渋谷の街を初めて歩いた瞬間なんて、言葉に表せないよ。だからあの交差点でやりたい(笑)!2日間封鎖して。マイケル・ジャクソン、レディオヘッド、ザ・キュアー、ジョイ・ディヴィジョン、デペッシュ・モード…。
――全バンド、ヘッドライナークラスじゃないですか~。
マーティン:そうだな~。じゃあ、あとはクールなエレクトロニック・アーティストをいくつか。僕はザ・フィールドの大ファンだから、彼にはダンス・テントに出演してもらって…(しばらく考える)色々な名前が頭をよぎってるから、考えるのにもっと時間が欲しいよ(笑)。
リリース情報
関連リンク
音楽を商業化している人々が昔のビジネス・モデルに執着しすぎて、
時代についていけてなかった

▲ 「Science and Vision」 (Session for BBC Radio 1)
――最近イギリスでは、ディスクロージャーなど90年代のエレクトロニック・ミュージックに影響された10~20代の若いアーティストが注目を浴びていますが、一世代上のマーティンには彼らの活躍がどのように見えていますか?
マーティン:面白い要素もあるし、エキサイティングだと感じる部分もある。18歳ぐらいの若者たちが、ハウス・ミュージックを知らずに育った同世代のキッズにその音楽を広めていると思うと、すごくシュールだけど。そういったダンス・ミュージックが全盛期だった90年代には、僕ですら子供だったけれど、イビザだったり、なんとなくそういうのが流行っているんだ、というのは認識していた。とは言ってもイビザに行くには幼すぎたけど(笑)。そういった音楽が再発掘され、現代の環境に蘇っているのは興味深い。一番いい所は、単なるリバイバルではなくて現在進行形で、現代の最新テクノロジーなど新たな要素が加わることによって、明らかに前進しているところ。それをディスクロージャーみたいに若い子たちが、積極的に行っているというのは素晴らしいと思うね。グラスゴーに関して言うと、ラッキーミーというレーベルがあって、彼らはグラスゴーにおいてのエレクトロニック・ミュージックの普及にすごく貢献している。
――やはりグラスゴーというとインディ・ポップの印象が強いけれど、考えてみればハドソン・モーホークなどのエレクロトニック・アーティストも多いですよね。
マーティン:うん、グラスゴーが音楽的に刺激的なのは、フランツ・フェルディナンドやベル&セバスチャンを輩出しているけれど、同時にハドソン・モーホークやラスティーなんかのエレクロトニック・アーティストもグラスゴー出身だ。それにポスト・ロックもグラスゴーにとって大きなムーヴメントだよね。
――モグワイとか。
マーティン:そうそう。だからグラスゴーで育ったというだけで、小さなコミュニティーのゆえに、様々な音楽を吸収できた。でも、やはり僕はエレクトロニック・ミュージックのシーンに一番シンパシーを感じるな。


▲ 「The Mother We Share」 (Live)
――グラスゴーの音楽やアート・シーンについて、もっと詳しく教えてください。創作活動をするのに適した環境だと感じますか?
マーティン:もちろん!親密なアート・コミュニティーという感じで、何かに携わっていれば大体知り合いだし、エキサイティングなプロジェクトも絶え間なく生まれている。歴史もあるから、過去に活躍したアーティストなどにインスパイアされて何かを始める若者たちも多い。これは80年代ぐらいから続いていることだと思うよ。オレンジ・ジュースやザ・パステルズのように、商業的に大ヒットしたバンドではないけれど、音楽的に認められているバンドも多いし。
――フランツ・フェルディナンドなんかは、オレンジ・ジュースにとても影響を受けていますもんね。
マーティン:一番いい例だよね。グラスゴーのとあるリハーサル・スタジオでは、フランツ・フェルディナンドに触発された若いバンドが、今頃リハを重ねてるんじゃないかな(笑)。
――では最後に、インターネットの普及によって大きな変化が起こっている音楽業界の現状についてはどのように感じていますか?
マーティン:僕はこれからもっと良くなっていくと思っているよ。最近ではレコード会社や業界が、有効にインターネットを活用できるようになってきた。メジャー・レーベルの経営状況から音楽業界は崩壊寸前なんて言われているけど、別にリスナーが音楽を聴かなくなったわけではなくて、音楽を商業化している人々が昔のビジネス・モデルに執着しすぎて、時代についていけてなかったからじゃないかな。それを一足はやく率先してやったiTunesなんかは、今優勢だよね。デジタルで音楽を買って、聴く為の理想的なプラットフォームを一番最初に作って、それが結果としてここまで成長した。後、アナログが復活の兆しをみせていることは個人的にとてもエキサイティングだよ。インディー・レコード店が軒並み無くなっている、という話を聞くけど、ラフ・トレードなんかは新たに店舗を開いているから、まだそのモデルには需要があるんだと思う。それにイギリスでは、アナログの売り上げが40%も上昇している。時間はかかったけれど、やっとみんなインターネットの有効な活用法が見いだせるようになってきたんじゃないかな。
リリース情報
関連リンク
ザ・ボーンズ・オブ・ワット・ユー・ビリーヴ
2013/09/25 RELEASE
HSE-60166 ¥ 2,608(税込)
Disc01
- 01.The Mother We Share
- 02.We Sink
- 03.Gun
- 04.Tether
- 05.Lies
- 06.Under The Tide
- 07.Recover
- 08.Night Sky
- 09.Science/Visions
- 10.Lungs
- 11.By The Throat
- 12.You Caught The Light
- 13.Strong Hand (ボーナストラック)
- 14.Broken Bones (ボーナストラック)
- 15.Gun -KDA Remix (ボーナストラック)
- 16.The Mother We Share -We Were Promised Jetpacks Remix (ボーナストラック)
- 17.The Mother We Share (Blood Diamonds Remix) (ボーナストラック)
- 18.The Mother We Share (Kowton’s Feeling Fragile Remix) (ボーナストラック)
関連キーワード
TAG
関連商品