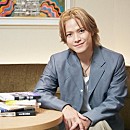Special
<インタビュー>音で闘う。レゲエで生きる――HAN-KUNの心に宿る火が次なる火種を灯す『VOICE MAGICIAN VI ~THE SIXTH SENSE~』

Text & Interview: 小松香里
湘南乃風のメインボーカルを担うHAN-KUNの5年ぶり、8枚目のオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI ~THE SIXTH SENSE~』。先行第一弾シングルの「Burn It Up」は燃え上がるような性急なダンスホールレゲエに乗せて、<熱くなりたけりゃ声上げろ><炎となって舞い上がるしかねぇぞ>といったエネルギッシュな思いとネット社会の「炎上」をリンクさせたメッセージソングだ。他にも「HEAD SHOT feat. SKY-HI」や「君となら…feat. RYOJI」、「Reggae Vibes feat. J-REXXX, APOLLO, 775 & Youth of Roots」といった既発のフィーチャリング曲を含め、レゲエをベースに多彩な楽曲が収められている。
レゲエの伝道師として、湘南乃風の活動と並行してソロ活動をスタートさせてから約15年。HAN-KUNの深いレゲエ愛と、衰えることのない前進しようとするエネルギー、ストレートに物申す辛くなってしまっている現代社会への警鐘などが詰まった新作の完成を機にHAN-KUNにインタビューした。
──コロナ禍にリリースされた前作『UNCHAINED』を経て、『VOICE MAGICIAN』シリーズの6作目がリリースされます。『THE SIXTH SENSE』と名付けたのは6作目というのが大きかったんでしょうか?
HAN-KUN:まさに6作目というところがありつつ、ソロ15周年の最終章にあたるアルバムなので、いい機会だと捉えて自分のキャリアを振り返ったんです。原点回帰ということを大切にしたいと思った時に自分が大切にしてきたのはステージだと改めて思いました。直感を頼りにアドリブやフリースタイルをやって、お客さんとコミュニケーションを取りながら生きてきた。アルバムをリリースしたあとには必ずライブをやりたいと思っていることとも紐づけて、第六感というタイトルにしました。
──「Burn It Up」を先行第一弾シングルにしたのはどうしてだったのでしょう?
HAN-KUN:ステージ上で自分の情熱や思いを言葉やメロディーに昇華して、お客さんたちの心に火を点けたいと昔から思っていたので、アルバムのコンセプトをわかりやすく伝えられる曲なんじゃないかと思いました。ライブでも冒頭で歌いたいと思っています。
──燃え上がるようなライブをイメージさせる曲であると同時に、昨今のネットでの「炎上」を想起させる曲でもありますよね。
HAN-KUN:そうですね。「炎上」ってそもそもネガティブな言葉じゃなかったと思うんですが、昨今ネット上ではネガティブな言葉になっています。俺がポジティブな意味合いでこの言葉を使うことで、ネット上のネガティブなバイブスに対するアンチテーゼになったらいいなって思いました。
──バーチャルな社会であるネットとリアルな現場であるライブの対比にもなっていますよね。
HAN-KUN:「以前説明しましたっけ?」って思うくらい理解してくださっていて嬉しいです(笑)。〈やってもねえやつがうるせぇ〉っていう歌詞もありますが、そういった言葉を発してはいけない風潮がありますよね。でも、生きていればそういう気持ちを抱くことって珍しくないと思うんです。思ったことをそのまま乗せられるのが音楽です。原点回帰というテーマに繋げると、自分が音楽を好きになった理由もそこが大きかった。誰かの曲を聞いて「なんでこの人たちは、こんなに俺のことをわかってくれているんだろう」って思ったり、自分の代わりに誰かに戦いを挑んでいるような曲に勇気づけられたりしてきました。自分が発信する側になったことの喜びを感じながらも、「昔自分が感じていたことを今の自分は発信できているのか?」とか「外からの目を気にし過ぎて、萎縮してしまっているんじゃないか?」っていう自問自答があったので、改めて自分の衝動をぶつけた曲になっています。
──「Burn It Up」と次の3曲目の「DO IT」は込められているエネルギーの質がとても近しいと思ったんですが、意図的だったんでしょうか?
HAN-KUN:「DO IT」は、「Burn It Up」からの流れを汲みたいと思って作った曲です。自分の根底にあるレゲエは、レベルミュージック(社会に反抗する音楽)です。その反骨心が「DO IT」と「Burn It Up」には強く反映されていますね。
──「DO IT」はオートチューンがかかったボーカルや多彩なアレンジなどから、ラガマフィンをモダンにアップデートしたような印象がありました。
HAN-KUN:拍手を送りたいくらい、素晴らしい解釈をしていただいていますね(笑)。というのも、この曲のビートは2010年にジャマイカで作ったもので、頭とサビとファーストバースくらいまではできたまま放置していたんです。今回のアルバムに合うんじゃないかと思って引っ張り出して、2010年代頃のラガマフィン強めのダンスホールに、レゲエの今のトレンドであるトラップダンスホールを融合させました。僕は何年もオートチューンを使っていなかったんですが、ここ数年流行っている僕も好きなアフロビーツやアマピアノの楽曲で使われていて新鮮に感じたので、本当に久々に使ってみました。
──2010年に書いたというファーストバースは〈止まらねぇ音と一生 立ち上がるぜ 倒れたっていくぞ〉という歌詞ですが、未だにこの気持ちが強くあるわけですね。
HAN-KUN:こういった気持ちが一番の原動力ですね。「この歌詞を書いた15年前と同じ気持ちで歌えるのか?」とも思ったんですが、今はいくつも職を持ったり、いろいろな選択肢がある時代です。でも俺は器用ではないし、自分が進んできた道を研ぎ澄ますように突き詰めていきたいと思ったんですよね。原点を大事にして生き続けて、家族を守り、仲間と笑っていられたら、この上ない幸せだと思った。そういう気持ちが、今歌うこのフレーズには込められていると思います。
通りすがりの人たちの足を止めて、ライブに引き込むのがたまらなく好き
──夢を掴み取るために戦い、仲間を思うエールソングになっている「Linky Dem」もレゲエがレベルミュージックであることを改めて強く感じさせる曲だと思いました。
HAN-KUN:アルバムを作るならど真ん中のオーセンティック・レゲエの曲も入れたいと思い、ジャマイカのミュージシャンから現地でスタジオ演奏した音を送ってもらって、日本でレコーディングして、それを戻して、ジャマイカにいる日本人の友達のエンジニアに完成させてもらいました。この曲で使われている「戦う」という言葉は、勝ち負けというよりは、レゲエを広げるという意味合いですね。レゲエは貧富の差が大きいジャマイカという国で、生きるために銃を持つかマイクを持つかっていうところから生まれた音楽です。日本からすると距離を感じるかもしれませんが、俺たちの好きなレゲエをどう日本に根付かせられるかを模索することが、俺や湘南乃風にとっての大きなテーマだと思っています。夢や目標に向かって葛藤することはレベルミュージックに込められていますし、家族や仲間を大事にする思いは、日本で生きる人たちにも共感してもらえる部分だと思いました。
──湘南乃風のメジャーデビューから22年、ソロは約15年活動していますが、レゲエの入口になれているという実感はありますか?
HAN-KUN:湘南乃風がよくやっている、レゲエ文化のひとつであるタオルを回す光景をライブ以外の場所で見ると純粋に嬉しいですね。湘南乃風のレゲエやダンスホール・レゲエの曲から俺のアルバムを聞いてくれて、クラブに行くようになった人の話も聞くので、この先そういう人がもっと増えたらいいなって思います。
──「夏のメロディー」は王道のレゲエのラブソングだと思いました。
HAN-KUN:気付いたらレゲエだったというような、多くの人が入ってきやすい「夏のメロディー」のようなレゲエの曲を、どんどん作っていきたいですね。音楽を始めた頃は「レゲエが最高なんだよ」って押し売りのようにしつこく言ってましたが(笑)、今は「なんかいい感じの曲が流れてるね」「これは実はレゲエっていってさ」みたいな順番になりましたね。そういう風に包み込むようにレゲエを伝えていきたいっていうか。昔の自分に「押し売りしすぎでうるせえぞ!」って伝えてやりたいです(笑)。グループとソロの二軸で活動させてもらっているのがとても幸せですね。グループで学んだことをソロに活かせるし、グループでやったことのないことをソロでやろうと思えることで、幅が生まれます。
──アルバムリリースの後には、インストアミニライブ&特典会とZepp Shinjukuでのワンマンライブが控えています。どんなことを楽しみにしていますか?
HAN-KUN:直接ファンの方に感謝を伝えられる機会はなかなかないので、ありがたいです。ワンマンと違って、インストアライブはアウェイでもあって。俺に興味のない通りすがりの人たちの足を止めて、ライブに引き込むのがたまらなく好きですね。「あのターバン巻いてるヤツなんなの?」って思った人が気付いたら写真を撮ってくれてたりするのもうれしい。レゲエに興味のない人にいかにレゲエを好きになってもらえるかっていう、自分がやろうとしていることを実際にできる最高のチャンスですよね。今まで培ってきたライブ力が試される場で修業でもありますね。
リリース情報

『VOICE MAGICIAN VI ~THE SIXTH SENSE~』
2025/7/23 RELEASE
<初回限定盤(CD+DVD)>
TYCT-69355 5,830円(tax in.)
<通常盤(CD)>
TYCT-60250 3,520円(tax in.)
再生・ダウンロード・CD購入はこちら
関連リンク
関連商品