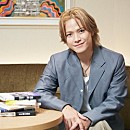Special
<インタビュー>冨田恵一、80年代をシミュレートした「透明な縁」の制作秘話とは――次世代プロジェクト“夢ノ結唱”連載Vol.2

Interview & Text:本間夕子
Photo:筒浦奨太
アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど、様々な展開を行っている次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」と人工歌唱ソフトとのコラボレーションからスタートしたメディアミックスプロジェクト『夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer』が、そうそうたる音楽クリエイター陣とタッグを組み、初のアルバム作品『CULTIVATION』をリリースする。
『Synthesizer V 2 AI』のAI技術によって「バンドリ!」に登場するアイドルバンド4組のボーカリストの歌声を再現した人工歌唱ソフト『夢ノ結唱 POPY・ROSE・PASTEL・HALO』を使用し、音楽クリエイターたちが思い思いに作り上げた個性豊かなサウンドがこれでもかとばかりに詰め込まれた今作は、まさしくAIと共存する未来のいち早い具現と言ってもいいかもしれない。そんな画期的作品において、とりわけ耳を惹くのがオーガニックな音像を基調として人工歌唱にアプローチした冨田恵一の楽曲「透明の縁」だ。音楽プロデューサーとして、作曲家・編曲家として多くのシンガー、アーティストに携わり、また、冨田ラボ名義でも数々の意欲作を生み出してきた彼はこのプロジェクトをどう受け止め、いかにして制作に臨んだのか。人工歌唱ソフトに対するスタンス、AIが普及する音楽シーンの行先についても、じっくりと話を聞いた。
「だからこそ試してみたかった」
――まずは今回のプロジェクトに参加されることになった経緯から教えていただけますか。
冨田恵一:大雑把に言えば、『夢ノ結唱 POPY・ROSE・PASTEL・HALO』を使って楽曲を制作してほしいという依頼をブシロードミュージックさんからいただいたんです。ボーカロイドをはじめとした人工歌唱ソフトのテクノロジー的な進化はなんとなくわかっていたし、今や、いわゆるボカロ的じゃない曲でもまったく遜色なく使えるんだろうなと思ってはいたんですよ。なので、これはいい機会をいただいたと思ってお受けしたんです。
――冨田さん自身も人工歌唱ソフトにご興味を?
冨田:『Synthesizer V 2 AI』ほど発達する以前の、フリーの音声ソフトは作曲時の仮歌用として何年か前から使っています。ただ、あくまでも仮歌なので言葉を歌わせることはしなかったんですよね。ラララとか、適当な英語をループさせるとか、それぐらいの使い方で。それでもなんとなく人間が歌っているような感じには聴こえるので、普通にシンセサイザーでメロディを奏でるよりもシンガーにはニュアンスが伝わりやすいんですよ。

――先ほど、いわゆるボカロ的なとおっしゃいましたが、そうした音楽に対してはどう感じていらっしゃったのでしょう。
冨田:正直、音楽性としてはあまり僕の興味を惹くようなものではないかなと思っていましたね。あくまで僕のイメージになってしまいますけど、8ビートでかなり高速のアッパーなサウンド、しかも高い音域を多用した音楽という印象で、そこから今度は生身の歌い手さんがいかに再現できるかで盛り上がるような、どこか競技的なニュアンスを感じていて。なので僕が普段やっている音楽とはジャンル的にあまり相容れないものなんだろうなという認識だったんです。歌としても、それこそ初期の初音ミクを起用した楽曲などを聴いていると、やっぱり人間のボーカルとは明確に違うものでしたしね。でも今回使った『Synthesizer V 2 AI』に関しては如実に進化していて、人声に代替可能なものになっているなという印象を受けたんです。
――たしかに今回のアルバムを拝聴して進化は明らかに感じました。
冨田:僕はボカロの歴史を追っているわけじゃないので、そこまで詳しいことはわからないですけど、その如実な進化は『Synthesizer V』が登場してからだという気がしているんですよね。まさに、そのあたりから作曲家仲間、アレンジャー仲間の間でも仮歌とかに一斉に使われ出したんですよ。ボカロ界隈に限らず、普通の音楽制作界隈でも使っている人が一気に増えた印象があって。僕が『Synthesizer V』を使うのは今回が初めてでしたけど、これは使うよなって思いました。それぐらい遜色がなかった。
――実際、制作をされるにあたって、どういったところからイメージを膨らませていかれたのでしょうか。
冨田:最初に(ブシロードミュージックの)スタッフのみなさんと打ち合わせをしたときに、人工歌唱ソフトだからといって特にそちら方面に振った曲じゃなくていい、むしろ普段の冨田さんが作る楽曲のようなものを、と言っていただいたんですよ。僕自身、そちら側に寄せるより、逆にまったく考慮しないで普通にシンガーに作るような曲を作ってブラッシュアップしていったほうが、このプロジェクトで僕が曲を書く意味があるんじゃないかと最初から考えていたので。
――とてもオーガニックなポップミュージックに仕上がっていますよね。すごく冨田さんらしいサウンドで、こうした音楽にも対応できるソフトなのか非常に驚きました。楽曲としてはある意味、今作の中でいちばん異色と言えるかもしれませんが。
冨田:そうですよね(笑)。僕も打ち込みっぽい曲を作ることはあるので、あえてそういう曲を作るのも面白いかなとは思ったんですけど、なるべくボカロ界隈とは離れた、よりオーガニックなサウンドのほうが今回の場合はトライし甲斐があるかなって。ストリングスなども取り入れつつ、ミディアム〜スローなものを作ろうというのはわりと最初の段階から考えていましたね。

――変な話、それはボカロ的なものに対するアンチテーゼとかではなく……?
冨田:アンチテーゼではないですね。今やジャンルとしてしっかり確立されていますし、そもそも否定する気持ちも全然ないですし。僕のルーツとはたしかに違うものですけど、むしろ、だからこそ試してみたかったんですよ。傍目に進化は感じていたけど、はたして人間のボーカルに対抗しうるものなのか、そこに関しては僕もまだわかっていなかったので。
――実際、お使いになってみていかがでした?
冨田:可能性はすごく実感しました。実は今回、歌詞の打ち込みに関しては、ブシロードミュージックさんにご協力いただいたんですよ。歌詞を打ち込むって今までやったことがない作業だったので、本当はそれも含めて全部覚えようと思っていたんですけど、締切と他の仕事の兼ね合いとでどうしても難しくて。何度かデータのやり取りを重ねながら作業を進めていったんですけど、より興味が湧きましたね。全部を自分で操作するようになったら、もうどんどん極められちゃう、キリがなくなっちゃうなって。
――素人な質問で恐縮なのですが、このソフトで歌詞を打ち込む作業って大変なんですか。
冨田:細かい発声のニュアンスを気にしなければ、さほど大変ではないと思いますよ。ただ、例えば“ら”の次に“た”がくるとか、音の並びによって発声がちょっと不自然になってしまって細かい調節が必要なので、むしろ打ち込んだあとの作業に時間がかかるんですよね。でも突き詰めようとしたらキリがない作業だけど、やる価値は十二分にあるなと思いました。
- 80年代アイドル×PASTEL&HALO
- Next>
80年代アイドル×PASTEL&HALO
――夢ノ結唱にはPOPY、ROSE、PASTEL、HALOと4タイプのキャラクター・声があって、冨田さんの楽曲ではPASTELとHALOを使っていらっしゃいます。この2つを選ばれた理由は?
冨田:最初は僕、HALO担当だったんですよ。HALOを使ってほしいというご依頼だったので、最初はHALOの声に合う曲をイメージして作っていったんです。で、ブシロードミュージックさんとやり取りをしていくなかで、もしかしたらPASTELを混ぜてもいいかもしれないというご提案をいただいて。実際に使ってみたら、思っていた以上にPASTELの声が曲調にぴったりだったんです。両方の声を交互に使って、最後は一緒に歌うという構成にしたら面白いなと思ったので、結局2人の曲になったという。
「透明の縁」
――着想の発端は声なんですね。
冨田:僕はそうですね。職業的に作曲や編曲をする場合は特に「この人の声がいちばんよく聴こえるのはどんな曲だろう?」「こういう声だから、じゃあこういう曲を書こう」みたいな順番で考えることが多いです。僕自身、歌ものが好きだというのもあるでしょうね。どうしても、どんな声の人が歌うかにとらわれてしまうんですよ。そのへんはシンガーに曲を提供しているのと同じ感覚でした、本当に。
――では制作もスムーズに?
冨田:はい。曲調がまず決まって、そこからはアレンジもほぼ同時にやっていったんじゃなかったかな。
――オーガニックな音像を基調としつつ、リゾート感というか、キラキラしたアーバンな聴き心地にちょっと懐かしさも覚えました。
冨田:20世紀のアイドルっぽい感じですよね(笑)。実際、80年代によく使われていたYAMAHAの『DX7』とか、キラキラしたシンセサイザーの音色をわりと使っているんですよ。夢ノ結唱の設定がアイドルバンドのボーカリストなので、そういうアレンジになりました。
――アイドルといえばやっぱり20世紀ですか。
冨田:20世紀というか、僕の世代でアイドルと言えばやっぱり80年代が全盛だったと思うんですよね。松田聖子さんや小泉今日子さん、そういった方々が活躍されていた時代で。当時、僕は20代で、それほどアイドルの仕事をしていたわけではないですけど、テレビというメディアが大きな影響力を持っていた時代でもあったから、どうやっても目にも耳にもするわけですよ。松本隆さんをはじめ、そうそうたる作家の方々が素晴らしい作品を生み出していて、音楽的にも豊かな時代でしたし。そうした時代をシミュレートした楽曲をHALOとPASTELの2人が歌うと考えたらスッと絵が見えてきて。わりと僕は16ビートの曲を作ることが多いんですけど、今回8ビートのゆったりした感じにしたのは、そういう理由でもあるんです。
――おそらく今回の企画で80年代アイドルを構想して曲を作られたのは冨田さんだけでしょうね。
冨田:だと思います(笑)。僕の認識だと、生身の人間が歌ってるって完全に言い切れるのは80年代までなんですよ。歌の切り貼りはエディット作業としてすでにやっていましたけど、それでもまだピッチを直したり、ビブラートをつけたりはできませんでしたから。そんな時代を感じさせるトラックを今のHALO、PASTELに歌わせるのが面白いんじゃないかなって。
ただ、作詞に関してはちょっと悩みましたね。それでお願いしたのが、僕がやっている冨田ラボに新しくシンガーとして入った北村蕗さんなんです。彼女自身、素晴らしい音楽家なので、きっといいものを上げてくれるはずだと思って相談したら、詞を単体で手がけるのは初めてだけど、ぜひやってみたいと快諾してくれて。
――なぜ北村さんにお願いしようと思われたのでしょう。
冨田:HALOとPASTELの年齢がいくつに設定されているのかわからないですけど、おそらく僕よりずっと若いはずなので、歌う言葉も同じ世代の女性が書いたほうがいいと思ったんですよね。大人の男性が若い女性の気持ちを代弁した歌詞を書いて、それをアイドルが歌うという構造はよくありますし、優れた作品もたくさん生まれていますけど、僕が手がけるのはそうしたフォームではないものにしたかったんです。

――歌詞というより詩と呼びたいくらい素敵な言葉が紡がれていますよね。「透明な縁」というタイトルもとても詩的で美しくて。
冨田:文学的な切り口を感じますよね。自分の未来を信じてポジティブに捉えた、ピュアでロマンティックな詞だと思います。僕からは特に注文は出してないんですよ。如実に可愛くなりすぎないほうがいいなとか、的外れに辛辣なことを歌わせたくはないなとは思っていましたけど、蕗さんならそのへんは何も言わなくても理解してくれるだろうと思ってお願いしたので。
――あまりアイドル然としたものにはしたくなかった?
冨田:歌詞に関してはそうですね。サウンドがアイドル全盛を想起させるものでも、歌詞の内容や歌い回しをアイドルっぽくさせたいとは思わなかったんです。HALOもPASTELも設定がアイドルですし、歌声も間違いなくそうなので、逆に発する言葉や歌のアーティキュレーションに関してはアイドルに寄せずにおくほうが、この曲の場合はいいものになる気がして。とはいえ、わざわざ“アイドル”という言葉を出して、“そうじゃないもの”みたいな言い方をしていたわけではないんですけど。
- 「聴後感を持ってもらえると嬉しいです」
- Next>
「聴後感を持ってもらえると嬉しいです」
――これまでにもたくさんのシンガー、アーティストとコラボレーションしてこられている冨田さんが、人工歌唱ソフトというものに対してどんなスタンスで臨まれるのか興味深かったのですが、完成した楽曲がまさに冨田恵一印の、実に記名性の高いサウンドになっているのがすごく面白くて。まったくアティテュードを変えていらっしゃらないのが驚異的ですらありました。
冨田:変えなくて平気だったんですよね。人工歌唱ソフトだからとか考える必要もないくらい、自分が書きたい曲を素直に書いて歌わせることができるんだというのは、今回、やり終えて僕自身も改めて認識した感覚なんです。それこそAIで作り上げた視覚的な人物像に『Synthesizer V 2 AI』で作った歌声を当てはめて「こういう新人です」って打ち出しても通用するんじゃないかなと思うくらい。これからクオリティももっと上がっていくでしょうし、学習元になる声のバリエーションが増えればさらに表現の幅も広がるでしょうし、非常に面白いなと思いますね。
――ちなみに、その場合の声というのは、冨田さんにとっては音楽を構築するためのツールになりますか? それとも、どこかやはり人格を伴った対象としての向き合い方になるのでしょうか。
冨田:ツールと人格を対比されると、ツールがすごく冷たく感じちゃいますけど、僕は生身のシンガーを録るときでも、その人の人格を録っているという意識はあまりなくて。この声でこういうふうに歌われるだろうから、こういうメロディを書いて、それに沿ったディレクションをして、という感じなんです。もちろん生身のシンガーの場合、その人格と対峙してはいるので「ちょっと休む?」みたいな配慮やコミュニケーションはしますけど(笑)。ソフトの場合、そういった部分はだいぶ省かれるでしょうけど、作るマインドは本当に何も変わらないと言っていいんじゃないかな。
――古い考えかもしれませんが、人間が歌うということが、音楽が生ものでいられる最後の砦だという意識がやはりどこかにあったりもするんですよ。なのに、こうして生の歌声と遜色ないものが人工で作れるとなってくると、この先はどうなってしまうのかなと一抹の不安がよぎってしまって。もちろんワクワクしてもいるのですけれど。
冨田:わかります。ただ、先ほど80年代の話をしましたけど、当時からすでに10トラックくらいあるなかから1音1音、声を切り出して歌を作るってことを僕自身、やってきているんですよね。その時点でもう生で歌われたものとは違うわけで、リスナーのみなさんが聴いているのは幻想であるということを作り手はみんなわかっていたんです。
さらに90年代になって『Protools』が登場して以降はもっと技術が進歩して、今やパパッと編集したものでもピッチやリズムが自然と合うように補正できてしまう。そうなると極論、シンガーは声さえ出てればいいってことにもなっちゃうんですよね。ピッチやリズムは完璧だけど声が出ていない人と、ピッチやリズムはヘロヘロでも声だけは出てる人だったら、後者のほうがより完璧な歌に作りやすい。それは音楽制作の現場にいる人間みんなが言うんじゃないでしょうか。少なくとも録音作品に関しては幻想だとわかったうえで楽しむものにそろそろなってきていると思うんですよ。

――そうなんですよね。
冨田:もちろん人によりますし、シンガーの方に聞いたらまた全然違う意見が出てくると思いますけどね。僕としてはもう、歌ものが本当に好きなので、録音作品に関して言えばトータルとしていいものを作りたいというマインドしかないんです。そして、そのマインドのなかに、生身の人間しかやっちゃいけない、みたいな感覚もないっていう。こういう声だとしたら、ここはこう歌って、こうフォールダウンするだろう、みたいなビジョンを持ちながら作るので、その通りにできたとしたら、ある意味、人格も含めて表現できたと言えるような気もしていて。
――歌そのもので人格を表現する、みたいな。
冨田:なので録音作品としての音楽という意味では、僕はだいぶワクワクのほうが勝ってますね。実際使ってみて「おお!」と思いましたし。
どうしても、2045年問題とかシンギュラリティとか、そういう議論になると、歌に限らずクリエイション全般において人間はいらなくなるかもしれないって話にもなっちゃうじゃないですか。でも僕はそこまで極論で考えてないし、悲観してもいなくて。そもそも作り手の個性とか細かいこだわりなんてリスナーの10%ぐらいにしか届いていなかったりするんですよ。なので残りの90%をAIに作らせたら、おそらくほとんどの人は満足するんです。ただ、それで満足しない人たちが今こうして音楽を作っているわけで、ビジネス的にはAIに負けたとしても、それでもなお作る面白さや楽しさはあり続けるので作ることをやめたりはしはないと思うんですよね。
――ぜひ作り続けていただきたいです。冨田さんが手がけられた「透明の縁」、リスナーのみなさんにはどのように聴いてほしいですか。
冨田:『Synthesizer V 2 AI』だとか、HALOだとかPASTELだとかは何も考えずに、曲が始まったら普通に歌ものとして聴いてほしいです。生身と遜色がなく普通に歌ものとして聴けること自体、本当に驚くべきことだけど、だからといって「AIの発達によって歌というものはどうなってしまうんだろう?」みたいなネガティブな感想は、この曲からはそんなに出ない気がするんですよ。そこが音楽の力だと僕は思っているので。さらに面白いことができそうだな、ワクワクするなっていう、そういう聴後感を持ってもらえると嬉しいですね。
冨田ラボ(冨田恵一)
音楽家、音楽プロデューサー、作曲家、編曲家。
冨田ラボとして今までに7枚のオリジナル・アルバムを発表。
長年に渡り冨田恵一のソロプロジェクトとして親しまれてきたが、2025年3月に新メンバーとして、Arche、北村蕗、santa(S.A.R.)、ヨウ(Natsudaidai)という4人のボーカリストが加入。新体制後初の楽曲「the birds of four」をリリース。4月には今年デビュー30周年を迎えるUAをフィーチャーした新曲「あはは feat. UA」をリリース。
音楽プロデューサーとしても多数のアーティストに楽曲を提供する傍ら、オーディエンスを前に楽曲を作り上げる「作編曲SHOW」や「Red Bull Music Academy」でのレクチャーなども実施。
自身初の音楽書「ナイトフライ -録音芸術の作法と鑑賞法-」は横浜国立大学の入学試験問題に採用された。
音楽業界を中心に耳の肥えた音楽ファンに圧倒的な支持を得るポップス界のマエストロ。
CULTIVATION
2025/07/16 RELEASE
BRMM-10953
Disc01
- 01.停止線上の障壁(バリア)
- 02.世界中に響く耳鳴りの導火線に火をつけて
- 03.Little Lazy Princess
- 04.汀の宿
- 05.ポータルB
- 06.Hatch
- 07.ヌード
- 08.antidote
- 09.流れ星のダーリン
- 10.比較言語学における陰謀的研究法の可能性について
- 11.最も濃いもの
- 12.マルカリアンチェイン
- 13.Singer
- 14.あなたなんて幻
- 15.手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ
- 16.私がマスター
- 17.すべてがそこにありますように。
- 18.透明の縁
- 19.Leap up Lollipop
- 20.心の愛
関連商品