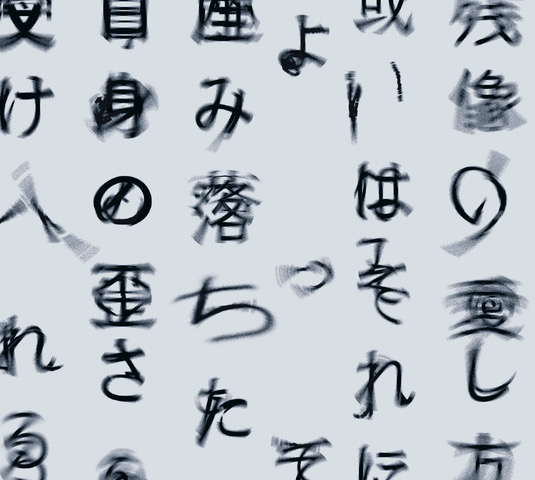Special
<インタビュー>残像を愛せるようになった――進化や変化を経て、Teleがいま歌うこと 全21曲収録の2ndアルバムを深掘り

Text:小川智宏
Photo:久保寺美羽
『「残像の愛し方、或いはそれによって産み落ちた自身の歪さを、受け入れる為に僕たちが過ごす寄る辺の無い幾つかの日々について。」』という、題名というよりは説明文のような言葉が冠されたTeleの2ndアルバムは、この2年間、アーティストとして進化し続けてきた彼の辿ってきた足跡がそのままに記録された、ドキュメンタリーのような作品となった。リリースと並行しながらライブやツアーを重ね、昨年には自身初となる日本武道館公演も実現させる中で、Teleの生み出す音楽は、描き出す風景の大きさも、その言葉やメロディが向けられる方向も、大きく変化してきた。このアルバム、とりわけ最後の3曲に宿る肯定的なムードは、Teleとは何を歌い、何を伝える存在なのか、その意味を改めてはっきりと示している。訪れた意識の変化と作品に込めた思いを、谷口喜多朗に語ってもらった。
“寄る辺の無い”日々の捉え方が変わった
――2022年の「Véranda」以降、2年間のTeleの軌跡というのがすべて込められたアルバムになりましたが、どんな手応えがありますか?
喜多朗:このアルバムはコンセプチュアルなアルバムかって言われたらそうではないんだけど、でも特にこの2年間くらいは、自分をそのまま人に認めてもらうんじゃなくて、自分を自分じゃない、ちょっと違う何かに変換させてみんなに受け入れてもらうみたいな作業をずっとやってきたんです。それがたぶんちゃんと「ポップス」を作るっていうことなんだと思うんですけど、その中で作曲やアレンジ、作詞の部分がルール化されていって、ようやく自分の中で守らなきゃいけないルールができあがっていった感覚。そのルールが作られていく過程みたいなものを1枚の中に収められたかなって。個人的には、聴いていると変遷が見られておもしろいなと思います。

――「Véranda」や「ロックスター」を作っていた当時の喜多朗くんと現在の喜多朗くんは明らかに変わっているわけですけど、当時の自分を振り返ってどんなことを思う?
喜多朗:うーん……その、「もっと自分ごととして考えたほうがいいよ」っていう(笑)。過去の自分が、別に不幸自慢とかをしたいわけではないけど、実家の家庭が変な感じだったんですよ。別にお金のある家じゃなかったし、住む家がなくて車で寝泊まりして学校に行ったりとかしたこともあったんです。その状態からテレビとかインターネットとかで成功している人たちの生活を見ると、ものすごく優雅で好き放題やっているように見えるじゃないですか。だから僕の認識からはその間、中間層の生活というものがごっそり抜け落ちていたんですよ。でも徐々に生活っていうものを見て、自分で経験していくと、そこにはグラデーションがあるんだと思えた。それから、今年25歳になるんですけど、それこそ同級生とかが同棲したり結婚したりするようになってきて。グラデーションが分からないから、「そんなにお金ないのに結婚していいのか」とか思ってたんですけど、そうでもないんだってわかったんです。自分と同じ世代の人間が当時の親くらいの年齢になって“普通”とされる生活みたいなものをしていくのを見て「それでいいんだ」って思った。
「Véranda」Music Video
「ロックスター」Music Video
――視界が広がっていろいろな選択肢が見えてくる中で、「それもあっていいじゃないか」と許せるようになったということなんですかね。
喜多朗:うん。アルバムの中で特に過去の自分のことを書いてるのが「砂漠の舟」なんですけど、本当に僕には、地元と呼ばれるものに対する“ふるさと”の意識みたいなものがなくて。本当に言葉通り“帰る場所”をずっと探してるというか。スタートがあって、ゴールがあってって考えて、そのスタートに僕は空洞を感じてたんです。じゃあ、そのスタートの空洞の代わりはいつになったらできるんだろう、どのタイミングで何の数字を出したらそこにたどり着けるんだろうって思ってた。でも帰れる場所はなくてもここにいていいんだって思えて、“寄る辺の無い”日々の捉え方が変わったことによって、“残像”を愛していけるようになれたっていう……だからタイトルは本当に説明文なんですよ。
――アルバムでいうと、「サイン」や「あくび」という曲はまさに残像を愛せるようになったからこそ歌えた曲な気がします。
喜多朗:「サイン」とかはアルバムの曲だなと思ってたんで、歌詞とかもそれこそ絞り切らないというか。〈綺麗だった。/ずっと、綺麗だった。〉っていうんですけど、綺麗だったからなんだっていうことは書かないようにしようと思ってて。でもそれがアルバムの中に入ることによって、タイトルの説明文に対しての補完になればいいなと思って。「あくび」は本当にクリックもなしで、いつもライブサポートしてくれている奥野大樹っていうキーボーディストと、スタジオにマイク立ててバンって録ったって感じだったんで、なんか生身すぎるからすごい恥ずかしいんですよね。

――でも、そういう成り立ちも含めて、「あくび」は谷口喜多朗という人間が呼吸しながら生きて生活をしているっていう感じがちゃんと曲になった感じがします。それこそ「砂漠の舟」で〈いつかぼくのままで海に会えたら〉っていう歌詞が出てきますけど、他の曲でも“僕のまま”とか“そのままで”とか、そういう類の言葉がいっぱい出てくるなと思ったんです。もう「これですから」ってポンと放り投げるような感じ。「ぱらいそ」の〈何にもなれないままで進む。〉とかもそうだけど。
喜多朗:そうですね。「ぱらいそ」は、俺の高校の時からの友達で、普通にサラリーマンとして働いてるやつがいるんですけど、激務で、めちゃめちゃ働いてたら電車の中でぶっ倒れちゃって。でも別に病気とかでもなく、ストレス性のようですって言われて2週間くらい休んだんです。そいつはもともと乗りこなすのがうまくて、普通に受験勉強やっていい大学入って就職先も行きたいところに行けちゃってっていうやつだったんですけど、そういうやつが初めて止まったから、挫折じゃないけど結構ガラッと変わっちゃうんじゃないかなと思ってたんです。でも実際会ったら、目が窪んでたりしている感じなのに、「俺、ヘラヘラ飄々と生きてきたんだけど、そういう自分は結構好きだから、また明日から働きますわー」って言って、普通に戻っていったんですよ。それがすごくかっこよくて、合理的だなと思ったんです。一見すると「いやいや、また過労になっちゃうよ」とか「精神的なトラウマみたいなのが残るから」とかって思うんですけど、このまま自分がいろいろ気にしながら穏やかな日々を生きるというのは、彼の定義からしたら全く理にかなってないんです。自分が好きじゃないんだから。その「今まで通り適当に生きるんだよ」っていうのが、「そうだわ」ってすごく思ったんですよ。その友達を見て「ぱらいそ」は書いたんです。でも、そいつのしんどさはたぶん解消はされてないんですよ。いわゆる世の中のルールから見たときのしんどさは。じゃあ俺がこいつに言えることってなんだろうって思ったら「マジで遊び尽くそうぜ」みたいな。

リリース情報
公演情報
【Tele 幕張メッセ公演(タイトル未定)】
2025年12月13日(土)17:30
神奈川・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
Tele 関連リンク
「先のことを歌おうよ」と思ってる

――「ぱらいそ」は“楽園”という意味で、実際歌詞には〈それでも僕らの楽園に朝が来る〉ともあるんですけど、その楽園だって文字通りの意味ではないですよね。
喜多朗:そう、僕らの楽園は本当にしんどいんです。しんどいんですけど、楽園なんですよ。「しょうがねえな」って半分諦め、半分受け入れるみたいな。昔から諦めの態度はあったんですけど、より軽々しくなったというか。今までは諦めを含めて笑うっていうことを悲劇として捉えていたけど、「そんなことないぞバカ野郎、楽しんだもん勝ちなんだから」みたいな。よりメタの部分で悲劇として捉えなくなった感じ。
――「ひび」でも〈あなたは、あなたの、日々を抱きしめて〉って言ってるけど、その委ねていく感じというか、相手の側に立ってその日常を肯定していく感じっていうのは今までと全然違うなと思います。
喜多朗:「ひび」を書いた時期はちょっと前なんですけど、いろいろ歌詞を書き直したりしても出しどころが分からない曲だったんです、ずっと。だけど今ようやくしっくりきている感じはあって。僕もあの曲すごい好きなんです。京成線っていう電車があるんですけど、本当に日中は誰もいないんです。僕、高校生の時に学校行くのが嫌だったんで、ずっとその電車を端から端まで乗るみたいなことをやってたんですよ。そうすると途中で障がい者の方とか、たぶん統合失調症の方とかが乗ってきたりするんですけど、何事もなかったかのように進んでいく。独り言とか言っている人がいても、誰も何も気にしていない。みんなあるがままそうあるだけだったから、すごい好きだったんですよ。そのときにこの曲は書いてて、その書き出しの部分だけずっと取ってあったんですけど、それが最近になってようやく自分にフィットしてきた。


――この曲の〈枯れた未来にお湯を注ごう。〉っていうのはどういうこと?
喜多朗:なんて言っていいんだろうな……たとえば乾燥したものにお湯をかけても元には戻らないけど、少なくとも乾燥してる時よりは食べやすくなるじゃないですか。元のようで元のものではない何かになるんですけど、絶対に枯れた時よりはいい。いいというか、本来あるべきだった形に近づくっていうことですよね。僕が音楽みたいなものを通してできることっていうのはそういうことで、直接的に時間を戻して正しい状態にはできないし本当に無力だけど、お湯を注いで限りなくそれのような何かにすることはできますっていう。それは老いた先でその人の皺を愛するみたいな、諦めでもあるんですけど、諦めた先の態度みたいなことなのかな。そういう意味ですね。取り返しがつかなくなってしまったものを元に戻す力はないんですけど、「それでもやらせちゃくれんかね」みたいな。

――その「ひび」から「砂漠の舟」、「ぱらいそ」っていうアルバムのラスト3曲は、どれもちゃんと未来を歌っているなと思うんですよ。今話してくれたように過去は変えられない、タイトルの言葉を借りれば“残像”は消せないしその形を変えることもできないけど、でも愛することはできるよね、それによって未来は変わっていくよねっていうことを歌っている気がして。
喜多朗:うん。僕たちの世代だと、過去も変えられないし、未来も変えられない、起きる事象っていうのはもう決定されていて、あとはそれをどういうルートを辿っていくか、その間の景色をどう楽しんでいくかっていう感性が強い気がするんです。でも、僕はやっぱり「だったら先のことを歌おうよ」って思ってるんですよ。どうせ悲劇は起こるし、どうせ苦しいことは起こるし、どうせつまんないことが続いていくんだから。僕はそれが本当に誠実な態度だと思ってます。だからそういうふうに未来を歌ってるって思われたらすごい嬉しいです。僕もそこを考えてたし。だから絶対に、それこそ「残像の愛し方」とかも〈愛したかったんだ。〉で終わりたくなるけど、〈愛していくからさ。〉で終わらなきゃダメだって。最後には絶対前に傾かなきゃいけないっていう自分の中でのルールがあったんで、そこだけすごい録り直しました。
「残像の愛し方」Music Video
――「砂漠の舟」も「ぱらいそ」も、まさに最後にいかに前を向くかに全てを懸けている感じがします。
喜多朗:曲によってはそれこそ1年前、2年前に1番だけ作ってて、そこから放置していたという曲もあって。それをどうにかして今の自分に合わせていかなきゃとなると、「おまえ、暗すぎ!」ってギョッとさせられたりもするんです。でもそれを無理に明るくするのは嫌なんで、正しくちゃんと前を向かせてあげる。それは乗ってるルートが間違ってるだけで、レーンを変えてあげれば、本当に進みやすくなるんです。このルートのまま明るくしたら嘘だけど、ずらしてあげれば自然と明るくなれるっていうこともあるので、そういう作業がアルバムの曲ではありましたね。
――それこそ「包帯」を書いたときは〈明日また、僕じゃないといいな。〉と歌っていた喜多朗くんだし、その気分は変わらないかもしれないけど――。
喜多朗:でもどうせ俺だし、「俺っておもしろいぞ」っていう気持ち。ちょっと人のせいにしてみるっていうのがあるんですよ。「まだ皆さん俺のおもしろさにお気づきじゃない? もっとおもしろいんですけどね」みたいな。今までは「俺が悪い」って感じで、自分のせいにしがちだったんですけど、ちょっと人のせいにしてみてもいいんじゃないかなと思った。「こうなっちゃったの、あんたのせいもあるんだからね」って。いろんなものを検証して「これはこのままでいいじゃん」って思えた部分もあるし、でも同時に変えた部分もめちゃくちゃあるし、なんか本当にちゃんと自分のままでいる、そのままでいるための力を得たんで。でも、なんかちょっと早く世界に変えられたいんです。もっといっぱい曲出して……今は僕のことを知って、好きでいてくれる人が集まってくれて、その数が増えている感じがするんで。なんか「本当の俺はそんなんじゃないのに」って言いたい。曲がバイラルヒットして、勝手に想像とかを押し付けられたいですよ。だって、それが売れるってことじゃないですか。だから……もっと誤解をしてほしい。

リリース情報
公演情報
Tele 幕張メッセ公演(タイトル未定)
2025年12月13日(土)17:30
神奈川・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール