Special
<インタビュー>細胞レベルで決められたレールと壁をぶち破る――星野源「生命体」を語る
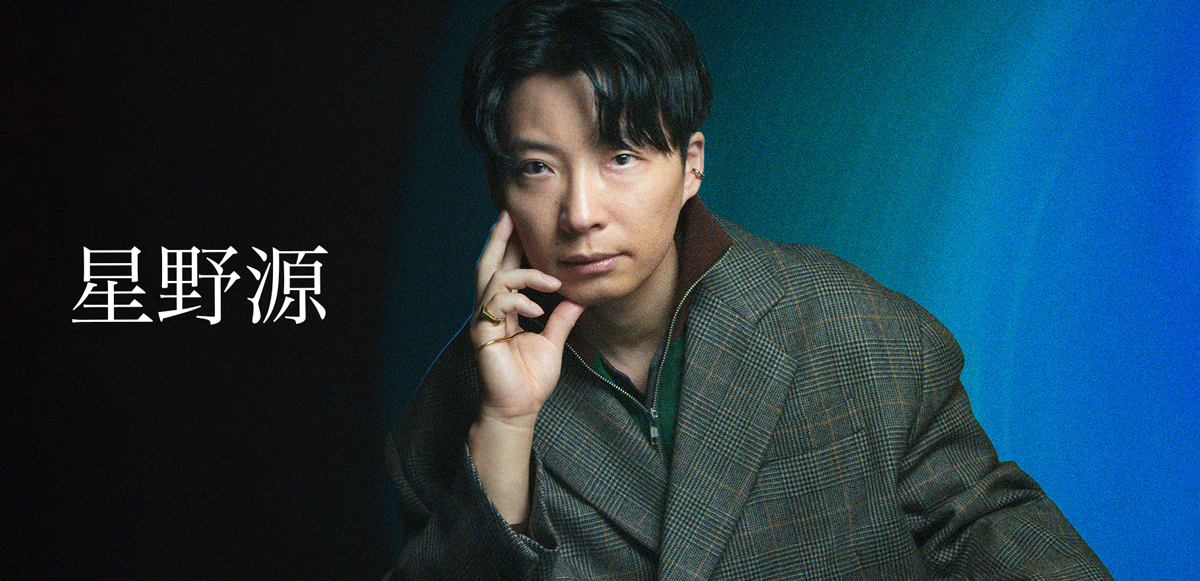
Interview: 高橋芳朗
Text: Mariko Ikitake
9月23日からアジア版オリンピックとも呼ばれる【アジア大会 中国・杭州】が開幕。200個以上のメダルを獲得し、日本全体を鼓舞した前回大会同様、今回も熱狂と感動の嵐が巻き起こりそうだ。
8月末に終幕した【世界陸上】に続き、【アジア大会】のテーマソングとして星野源「生命体」がオンエアされる。星野自身の気持ちが投影されたこの曲が、選手、視聴者、リスナーにどう寄り添うか、そしてどう受け取られるかは、一人一人に委ねられる。制約やしがらみの中でもがき、苦しみ、どこまでそれをぶち破れるか――一曲に込められた星野の強い意思と本音がインタビューを通して明かされた。
――まず、【世界陸上 ブダペスト】と【アジア大会 中国・杭州】のTBS系テーマソングのオファーをもらった際の率直な心境を教えてください。
星野源:【世界陸上】と【アジア大会】の両方のテーマソングだったのがすごく意外でした。コロナの影響で延期になったこともあって、同じ時期に開催されることになったそうで、そんな特別なタイミングでオファーをいただけたことがすごくうれしかったです。特に【世界陸上】は次の時代に向けて新しいイメージのものを作りたいとのことだったので、そういう意味でやり甲斐も感じました。ただ単に依頼を受けて曲を作るのとはちょっと違う感じがしたというか。いままでとは違う、また別のところに行こうとしていること、同時にふたつの大会が重なっていることも含め、おもしろいと思いました。
――星野さんはこれまでにも東京オリンピックを見据えたACジャパン「ライバルは、1964年」キャンペーンの「Hello Song」だったり、スカパー!「リオ2016パラリンピック専門チャンネル」テーマソングの「Continues」など、スポーツにちなんだイベントに楽曲を提供してきました(共に2016年。収録アルバムは2018年作『POP VIRUS』)。この2曲の存在は今回のテーマ曲の制作に取り組むにあたってなにか影響を及ぼしていますか?
星野:「Continues」のほうがつながりは強いと思います。「Continues」は、大会や選手の皆さんの思いをしっかり曲に組み込みつつ、同時に当時の自分の音楽家としてのメッセージだった「音楽の継承」のようなものも落とし込んでいて。そのうえで、スポーツというゲームをどう解釈して曲にしていくのかを考えていきました。大会が終わってもゲームは続いていくし、それで人生が終わるわけでもない。そういう「Continues」のテーマは今回の「生命体」ともつながっているというか、ほぼ同じと言ってもいいかもしれません。
――7月4日放送の『星野源のオールナイトニッポン』では今回のテーマ曲を制作するにあたって陸上やスポーツを勉強し直したと話していましたね。
星野:NHK大河ドラマの『いだてん~東京オリムピック噺~』(2019年)で平沢和重(1959年のIOC総会で東京オリンピック招致のための最終スピーチを務めた外交評論家/ジャーナリスト)を演じたときに日本におけるスポーツの成り立ちや、それによって日本人はどう元気づけられていったのか、といったところはすでに勉強していて。今回は現代のスポーツがどのように発展していったのかを知りたくて勉強したんですけど、陸上競技を取り巻く状況って、すごくメジャーだし馴染みのあるスポーツだけれど、決して強化費が潤沢にあるわけではない種目もあるから、厳しい立場に置かれている選手の方もいる。やり投げの北口榛花選手が金メダルを獲った直後のインタビューで「自分が必ず歴史を作ると心に決めてここにやってきた」とお話していましたけど、その言葉の重さは、実情を少しでも知っていると本当に重い言葉として響いてきます。北口選手の活躍によって、やり投げの競技人口もぐっと増えるでしょうから、あの瞬間、歴史の1ページだけでなく、未来も作ったんだと思うんですよね。
――こうした流れを踏まえて、どういうヴィジョンをもって曲の構想を膨らませていったのでしょう?
星野:最初に思い浮かんだのがゴスペルだったので、ゴスペルをどう表現するか、から考えていきました。どのスポーツにも共通すると思うんですけど、陸上は特に自分との戦い、メンタルスポーツ的な側面が強いじゃないですか。それを踏まえるといわゆる応援ソングだったり、ひとつのものが絶対正義である、みたいな歌はちょっと違うなと思ったんです。そこで思いついたのが、自分の力や個人の心と体を最高の状態に持っていく歌だと。プレッシャーだったりエゴだったり、いろいろなものに縛られている日常から解き放たれて……孫悟空が重い道着を脱ぎ捨てる状態、みたいな(笑)。そういうモードになれる歌、それこそすごく元気が出て血が沸き上がるようなテンションになれる歌というか。そういうヴィジョンが最初にありました。
――そういうイメージにゴスペルミュージックが合致したと。
星野:そうですね。選手の方がゾーンに入ったときの感覚は、きっとゴスペルが持つトランスしていくような感覚と共鳴するはず、という確信があって。ただ、一般的にイメージされるゴスペルとはちょっと違うものになるだろうとは思っていました。
――自分が知る限り、日本のスポーツ番組のオリジナルのテーマソングとして「生命体」のようなゴスペル色の強い曲はちょっと他に思い当たらなくて。意外かつ、とても新鮮なアプローチだと思いました。
星野:ありがとうございます。もう普通のものが上がってこないであろうことは、僕に頼んだ時点で了承済みだと思うし、それはもうしょうがないですよね(笑)。
――「生命体」のゴスペルなイメージを決定づけているのは、やはりサビのコーラスとハンドクラップによるところが大きいと思います。ここではUAさんのキャスティングが目を引きますね。
星野:UAさんを提案してくれたのは、UAさんも担当している僕のディレクターでした。いつもは僕と亮ちゃん(長岡亮介)のふたりでコーラスをやっているんですけど、一回歌ってみたあとに、もう少し違う要素がないといまいち盛り上がらないと思い、誰か呼べないかって話になったんです。そうしたらディレクターから「UAさんはどうですか?」って。確かに言われてみればUAさんしかいないんじゃないかって思えてきたんです。UAさんって、もうソウルの蛇口が自分の井戸と直結しているような方じゃないですか。海外から水道管を引っ張ってきて、そこに蛇口を付けてソウルを出しているのではなく、自分の実家にある井戸からソウルを出して歌っているような人だと思うんですよ。ただ、複数人で歌うことになるので、UAさんの声は単体では認識できないようなミックスになるだろうと。でも「そのほうがきっと本人は気楽に楽しんでやれると思う」と言われ、ダメもとでオファーしてみたら快諾してくださったんです。
――そして、UAさんが加わったことによってコーラスの仕上がりが一変したと。
星野:本当に変わりました。僕が歌を作るときは言葉と同じくらい、言葉じゃない音の感覚を大事にしていて、UAさんがそこを強烈に担ってくれて、この曲の持つパワーを底上げしてもらいました。
――ゴスペル感ということでは、コーラスと共にハンドクラップの存在が活き活きとした躍動と祝福を生み出していることにも感動しました。
星野:楽曲自体はもともとすべて打ち込みで作っていたので、クラップも最初はぜんぶ打ち込みでした。そのあと生音に変えていったんですけど、今回の制作では生音を使いながらも「生音だから良いわけではない」ということを証明したくて、クラップは生をちょっと重ねているぐらいで実はほぼ打ち込みなんです。「生命体」を聴いて「やっぱり生音っていいね!」と言う人が大勢いると思うんですけど、生じゃない部分も実はいっぱいあるという(笑)。打ち込みでもパッションや衝動は生み出せる、ということを意識して、クラップを打ち込んでいる時点からパッションを感じられる音選びを心掛けていたので、ハンドクラップが活きているのもそのお陰なんだと思います。
リリース情報

「生命体」
2023/8/14 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら

EP『LIGHTHOUSE』
2023/9/8 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら
関連リンク
――「生命体」を一聴して驚いたのは、一般的なクリアでパキッとしたサウンドとは一線を画した音処理です。特に石若駿さんが叩いているドラムに顕著ですが、このローファイともスモーキーとも言える生々しいガレージ感が確実に曲のヤバさに拍車をかけていると思っていて。
星野:きれいにマイキングして、きれいに録音して、きれいにミックスしていくという音作りに飽きてしまったんです。日本のミックスって整合性だったりコスト・パフォーマンスだったりタイム・パフォーマンスだったり、いろいろなことを突き詰めていくスタイルが多いんですけど、それをやっていくとつまらなくなっていくと思ったので、いびつなものを作ろうというコンセプトが最初からありました。たとえば、武嶋聡さんのサックスは彼の自宅で録っているんですよ。ちゃんとしたスタジオで潤沢なプリアンプを使って録っていなくても、すごくパワーのあるサックスですよね。
――あのサックスが鳴る瞬間の祝祭感は本当に素晴らしいですね。「YELLOW MAGAZINE+」(星野源の公式メンバーシップサイト)のレビューでも書きましたが、「生命体」の大きな魅力のひとつと言っていいと思います。
星野:「良い音できれいに」とか「ヴィンテージの機材を使って」とか、そういうことが生命力やパッションにつながるわけではなくて、その音の中にある、それこそ魂みたいなものが大事なんだっていう当たり前のことを立証したい気持ちが強かったんです。そんなことを最初から最後まで突き詰めたのは今回が初めてでした。ドラムのマイキングもこれまでとまったく違うやり方で。まずきれいに録音して、エフェクトでローファイに変えたり音を汚くしていったりするのがいまの主流なんですけど、もう最初からきれいなところに戻れない状態で録ってる(笑)。ある意味、自由がない状態で作っていくというか。サックスにしても最初はすごく良いマイクを使ってレンジの幅を広めに録音して、そこから縮めてローファイにしていくやり方が多いんですけど、元から広げようがない状態で録ってそこからどうしていくかを考えるという。いまの一般的なレコーディングとは逆の手法で作っていきました。
――ミックスを担当している渡辺省二郎さんがご自身のInstagramで「ドラムはグリン・ジョンズ・スタイルで録りました」とうれしそうに書かれていました(グリン・ジョンズ:ザ・ビートルズ『レット・イット・ビー』、ザ・ローリング・ストーンズ『スティッキー・フィンガーズ』、レッド・ツェッペリン『レッド・ツェッペリン』、ザ・フー『フーズ・ネクスト』など、数々のロック名盤でエンジニア/ミキサーを務めてきた英国ロックの重鎮)。
星野:省二郎さんとはもう10年以上一緒にやっていますけど、あんなに楽しそうにしていたのは初めてでしたね(笑)。「とにかく早くみんなに聴いてほしい!」って言っていました。
――星野さんとmabanuaさんによるアップライトピアノの弾け方もとても心地よくて。星野さんの好きなトミー・フラナガンだったり、ゴスペル的/リズム&ブルース的というところでは1960年代のラムゼイ・ルイスの演奏を連想したりもしました。「生命体」からはゴスペルのエッセンスを強く感じつつも、星野さんがルーツとして内包しているジャズの要素も表面化しているように思います。
星野:そうですね。今回はピアノを使っているのと楽器が少ないこともあってヴォイシングの普通じゃなさや和音のコード・プログレッションがすごくわかりやすいと思うんです。僕の中では「ジャズをやるんだ」って気持ちはぜんぜんなかったんですけど、自分の中で鳴っている音がピアノとベースとドラムというコンパクトな編成だったこともあって自分のルーツみたいなものが混じり気なく伝わったんだと思います。
――個々の楽器の力強い存在感に対して、星野さんのヴォーカルは風のようにふわっと柔らかくて軽やかで。でもしっかりソウルとパッションが宿っていて、演奏とのコントラストが絶妙です。
星野:今回のキーはいつもよりかなり高いんです。一生懸命に力を込めて歌ったほうがタイトルの「生命体」のイメージに忠実で、よりわかりやすくなると思うんですけど、それよりも間をスルスルとすり抜けていくような歌い方のほうが、曲としてオリジナルなものになると考えました。「ソウルっぽくやるぞ!」っていう思いでやってしまうと、急につまらないものになる。自分の歌い方、自分にしかできないテンションで歌いました。あと、今回は歌詞を伝えることよりも、フロウ、歌い方を大事にして、言葉より先に音が先に入ってくるようにしました。
――お話を聞いている中で今回の制作にあたってのテーマみたいなものがいくつか挙がりましたが、曲を完成へと仕上げていくに際してどんな点に苦心しましたか?
星野:楽器を少なくすることに対して、心の中では「絶対にそのほうがいい!」と思うんだけど、頭は「大丈夫かな?」「いまの日本で受け入れてもらえるだろうか?」と考えてしまうんです。この音数と響かせ方は日本ではあまりないから、どうしても「もうちょっと安全策をとったほうがいいのでは?」っていう考えが頭に浮かんでしまう。でも僕が聴いていて好きで楽しいのはこっちなので、そのままにしました。そこの踏ん切りをつけるまでにちょっと迷いがありましたね。
――最終的には振り切ったわけですね。
星野:そうですね。あと、一番の歌が終わったあとですぐにサックスソロが入るような構成もあまりないんですけど、そういうシンプルだからこその仕掛けやポイントをいっぱい詰めていきました。自分が飽きないように工夫したって感じですね。
リリース情報

「生命体」
2023/8/14 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら

EP『LIGHTHOUSE』
2023/9/8 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら
関連リンク
そこには自由がないから
それを破壊するような曲を作りたかった
――星野さんは今回の新曲のタイトルが「生命体」に決まった経緯について「フィーリング」「なんとなく」とラジオで話していましたが、〈"1"を超えた先〉というフレーズに象徴されるエゴを突破した先の状態を綴った歌詞を素晴らしい躍動感の演奏に乗せて、ゴスペルという魂の解放の音楽を通して表現したことを考えると、やはりこれは絶妙なタイトルだと。
星野:ありがとうございます。
――いままで特に向き合ったことはありませんでしたが、「生命体」という言葉には小さくとも個々のプリミティヴなパワーや生への執着が秘められていることに気付きました。
星野:人って生まれてから割とすぐに決まったレールに乗せられるというか、そのレールの上での自由を自由と感じていると、ふと考えたんです。歌詞の〈風に肌が混ざり溶けてく〉という部分は自我が消えた瞬間を表していて、タイトルよりも先にその歌詞ができあがっていました。細胞レベルにまで思いが達するというか、そこに意思や遺伝子のレールを感じるんですよね。あらかじめ決まってしまっているなにかがあるというか。人間だけじゃなくて、生物全体、感情が見えないような微生物にも社会のレールみたいなものが存在していて、そこから逃れようとしても逃れられない、なにか決まってしまっている上で生きているのは、どの生物もみな一緒なんじゃないかと思ったんです。それでタイトルとして「生命体」がぴったりだなって。現代を生きる人間を歌っていること、「生きる命の体」と書くタイトルは、フィジカルスポーツとの相性もバッチリだと思いました。
――いまのお話は最初に触れた「Continues」だったり、星野さんがこれまでに発表したゴスペルの要素を取り入れた曲、たとえば「生まれ変わり」(2013年作『Stranger』収録)や「Soul」(2015年作『YELLOW DANCER』収録)にも通底するところがあるように思います。
星野:確かにそうですね。ゴスペルを取り入れるときに思っていることは、自分はクリスチャンではないから生半可な気持ちではやれないということと、真似になってはいけないということです。僕はゴスペルを聴くのも歌っている人たちを見るのも大好きで、人間のパワーを感じるので憧れもあるんですけど、そのままやってしまうのは失礼だっていう気持ちがずっとあるので、これまでストレートなゴスペルをやったことはないんです。「生まれ変わり」もゴスペルにインスパイアされてはいるけど、音楽的にも歌詞の思想的にもちょっと違うものですし。小学生の時から好きで聞いていたゴスペルは、リアルなものとして自分のハートの中にはあるけれど、その気持ちを自分の環境や音楽のセンスで濾過して表現すると自ずとそうなっていくんですよね。今回の「生命体」もロジックとしては明らかにゴスペルではないんですけど、芳朗さんがこの曲から自然とゴスペルを聞き取って「YELLOW MAGAZINE+」のレビューで書いてくれたように、僕がなにも伝えていないのにゴスペルを感じてくれる人がいるのはすごくうれしいことですね。
――星野さんの最近の作品でいくと、映画『CUBE 一度入ったら、最後』(2021年)の主題歌「Cube」の2分50秒以降のサウンドや歌詞が「生命体」につながっていくようなところがあると思っていて。
星野:2分50秒以降(笑)! 細かい! 「Cube」は自分にとって衝動のかたまりみたいな曲なんです。「生命体」が受け入れてもらえるかどうか不安な部分もあったと、さきほど話しましたが、割と一気に浸透したのは「Cube」を経ているからかもしれませんね。去年アメリカに行ったときにジェイムズ・ポイザー(ヒップホップバンド、ザ・ルーツのメンバー。プロデューサー/ソングライターとしても数々のヒット作に関与してきたフィラデルフィアのヒップホップ/R&Bシーンを支える重要人物)とジャジー・ジェフ(1980年代から活動を続けるヒップホップDJ界のレジェンド。フレッシュ・プリンスことウィル・スミスとのコンビで一時代を築いた)、それからジェフの友人のミュージシャンたちとセッションしたり曲を聴き合ったりしたときに「Cube」も聴いてもらったんですよ。そうしたら、みんなめちゃくちゃうれしそうで。ジェイムズ・ポイザーは教会で演奏していたこともある本物だから、そんな人たちが「お前、イカれてるな! 最高だよ!」って褒めてくれて(笑)。「Cube」は僕のファンや音楽マニアの人たちには刺さったんですけど、それ以外の方たちにはあまり理解してもらえなかった。でも、ジェイムズやジェフに伝わったことがめちゃくちゃうれしくて。やっぱり、ゴスペルをただ真似しただけのものだったら彼らに聴かせてもすごくシラけていたと思うんですよね。ふたりの反応を見て、間違ってなかったって思えました。
――「生命体」の登場によって「Cube」の聴かれ方が微妙に変わってくるんじゃないかと思っているんですよ。
星野:それはあるかもしれませんね。「生命体」も伝わるのにもっと時間がかかると思っていたんですけど、まったくそんなことがなかったので逆に面食らいました(笑)。
――あと曲の全体的なところについてですが、星野さんは世界陸上の開幕前、TBS陸上ちゃんねるのインタビューでシェリー=アン・フレーザー=プライスについて話していましたよね。
星野:はい。
――「彼女はすごく自由な感じがする。ああいう場所で自由でいられる、自由なように見えるということは、めちゃくちゃ戦っている証拠だと思う」と。このコメントを聞いたとき、従来のスポーツ番組のテーマ曲に新しいイメージを持ち込んだ星野さんも同様にめちゃくちゃ戦っているというか、めちゃくちゃ自由を求めていると思ったんです。そういう星野さんのスタンスも含め、「生命体」はサウンドにしろ、楽器にしろ、歌詞にしろ、曲全体が「自由」を謳歌しているように響いてきて。「生命体」の歌詞には〈無自由な運命も 愛と 変えるの〉との一節もありますが、「自由であること」が「生命体」のキーになっているようなところはありますか?
星野:すごくあると思います。とにかくいま、社会の風潮だったり、インターネットの中であったり、そういうものからの抑圧しか感じていないし、自由をまったく感じられないんです。そんな状況だと自由を求める曲ができてしまうのは、自然なことだと思います。正反対の環境に置かれているからこそ作ることができる。同じように、音楽も誰かが作った道筋をみんなが通っている感じがするんですよ。その中でみんな一緒に安心しながら楽しんでいるというか。でも、僕にとって、それはまったく楽しいものではなくて。そこには自由がないから、それを破壊するような曲を作りたかったという気持ちがすごくありました。
――なるほど。
星野:なんか、社会や世間と対峙すると、生きたいと思えないんですよね。数少ない自分の信頼している人や仲間と接しているときだけはそう思えるけど、世の中を見ると「生きたい」とか「未来が楽しみで楽しみでしょうがない」みたいな気持ちがまったく起きない。だから「生命体」の歌詞には〈死ぬな〉って言葉が出てくるし、「僕はここにいないほうがいい」という感覚がすごくあるから〈あなたは確かにここにいる〉って歌っている。それは、自分がそう言ってほしいからなんです。もちろん頭ではわかっているんですよ、自分は実際に存在しているって(笑)。本来は、いまこの場所でみんな堂々と朗らかに生きていいんだと思っているからこそ、そういう歌にしました。
――星野さんは世界陸上のテレビ中継を毎晩夢中になってご覧になっていたようですが、実際に競技の映像と共に流れる「生命体」を目の当たりにして曲に対する新たな発見や気付きはありましたか?
星野:世界陸上のテレビ中継では、その日に行われた競技の模様が1分ぐらいのダイジェストになって「生命体」と一緒に流れるんです。いつもテレビを見ながらそのエンディングを楽しみにしていて、自分が考えていた以上に曲が合っていてうれしかったのと、選手の皆さんが最高潮の状態に向かう瞬間との共鳴を感じたので「間違ってなかった!」と思えました。あと、400mリレーで日本が決勝進出を果たしながらも最終的にメダルに手が届かなかった日のダイジェストの最後は、リレーの選手たちの顔を映して終わったんですけど、結果に対してまったく納得していなかったサニブラウン(・アブデル・ハキーム)選手の表情が笑顔でもなく泣いているわけでもなく、悔しさだったりいろいろな感情がないまぜになった真顔だったんですよ。そんなサニブラウン選手の表情に「生命体」の最後の歌詞〈そして つづく〉がオーバーラップしたところでダイジェスト映像が終わったんですけど、その瞬間に新しいスポーツの曲を作ることができたって思いました。競技の中のそういう一瞬が、決してそこで最後ではなく続いていくものだということを提示できたと思えました。金メダルを獲った瞬間に流れても、悔しい思いをした選手の表情に合わせて流れても、どんな場面でもこの歌は響くことがわかったとき、すごく嬉しかったですね。
リリース情報

「生命体」
2023/8/14 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら

EP『LIGHTHOUSE』
2023/9/8 DIGITAL RELEASE
再生・ダウンロードはこちら
関連リンク
関連商品
































