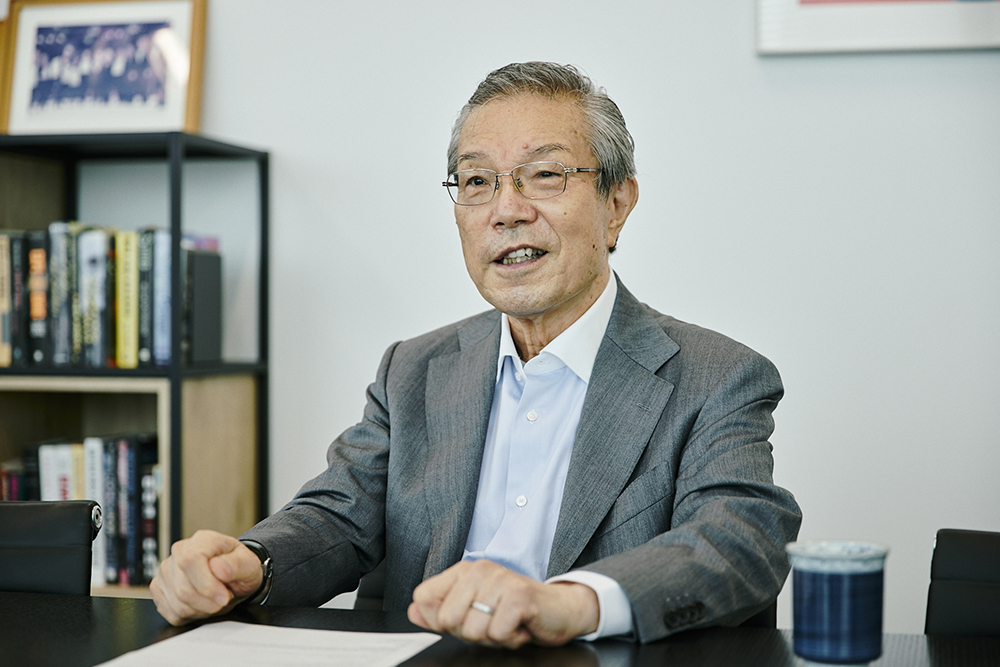Special
Billboard International Power Playersインタビュー vol.1 朝妻一郎 フジパシフィックミュージック会長

米ビルボード誌が、アメリカ以外の国で音楽ビジネスの成功を牽引しているリーダーを称える【Billboard international power players】。各国から音楽業界を牽引するリーダーが選ばれた中、50年以上にわたり日本の音楽業界に貢献したことが称えられ、株式会社フジパシフィックミュージック 朝妻一郎会長が選出された。ビルボードジャパンでは、本表彰を記念し、朝妻会長へインタビュー。日米でのビジネスの違いや、今後の音楽シーンに期待することなど、50年を振り返りながら話を聞いた。
50年間大切にしていること、原盤制作にも出資するようになった経緯
ーー日本の音楽業界の中心人物として、貢献されてきたことが称えられパブリッシング部門で選出されました。この50年、大切にしてらっしゃることは何ですか。
朝妻一郎:洋楽、邦楽問わず、良い曲をいち早く探して、その権利を獲得するということです。もともと僕は音楽業界ではない会社で働きながら、音楽評論家のアルバイトをしていました。そんなことをしているうちに、ニッポン放送から「音楽出版社を作るから、手伝わないか」と誘われて。当時、音楽出版社の存在は知っていましたが、一体何をしている会社なのか、全然知りませんでした。そこで、ウィリアム・クラジロフスキーが書いた『This Business of MUSIC』という本を読みました。そして、おぼろげながらも「そうか。良い曲、良い曲を作る作家、そしてその良い曲を歌うのにぴったりのアーティストをいち早く探すことが命題なんだな」ということが分かって。この会社で働き始めて55年が経ちますが、その考え方は変わっていません。
ーー会社を立ち上げられた当時は、洋楽/邦楽どのような割合でビジネスをされていたのでしょうか。
朝妻:洋楽がメインでしたね。そもそもパシフィック音楽出版(後のフジパシフィックミュージック)を設立した1966年、日本での音楽の売上は、洋楽の方が多かったと思います。当時、日本のレコード会社には専属作家がいました。なので著作権もレコード会社が持っていて、我々は参入できなかったんです。我々が著作権を管理できる曲は、フリーの日本人作家もしくは海外の曲しかなくて。パシフィック音楽出版を音楽出版社としてJASRACに登録したのは115社目だったと思うのですが、当社以前の114社についても、邦楽の著作権管理だけでビジネスを成り立たせているところはなかったと思います。ですのでアメリカやヨーロッパの楽曲のサブパブリッシャーとしての仕事が、ほとんどでしたね。
ーー洋楽の著作権を管理し、プロモーションしていく上で難しかったことは何でしょうか。
朝妻:当時は、とにかくラジオの影響力が絶大でした。レコード会社が、それぞれ自社の曲をプロモーションするための番組を持っていたんです。ビクターは『S盤アワー』、コロムビアは『L盤アワー』、キングレコードは『魅惑のリズム』、ポリドールは『P盤アワー』ですね。なので新たな楽曲の権利を獲得できると、まずレコード会社に「この曲をリリースしてください」と頼みにいきます。そして、次はラジオ局に行って「この曲をかけてください」って頼むんです。当時、1曲あたりの録音印税は7円20銭でした。なので、ラジオ局に対するプロモーションがメインでしたね。
ーー御社は楽曲の管理のみならず、原盤制作にも出資されるなど、幅広いビジネスを展開されています。そのような音楽出版社は珍しいのではないでしょうか。
朝妻:そうでもないんですよ。当時、洋楽のサブパブリッシング契約には「楽譜を発売すること」「カバー曲をリリースすること」の2項目が含まれていました。大ヒットした曲だったら、インストゥルメンタルのアルバムをリリースしているレコード会社に頼めば済みますが、ヒット曲のB面に収録されている曲の場合、それは受け入れてもらえません。なので、必然的に自分たちでカバー曲を制作してリリースする必要がありました。音楽出版社が原盤を制作するというのは、ある種 当然の道筋のようなものだったんです。
ーーそうだったんですね。
朝妻:もう1つの理由としては、先ほど申し上げた通り、レコード会社は専属作家を抱えています。なので、我々が新しいアーティストを探してきても、レコード会社としては「じゃあ、当社の作家に、このアーティストの楽曲を作らせましょう」となるわけです。ですが、我々が探してきたアーティストがシンガーソングライターというケースもあります。なので自社で原盤を制作し、レコード会社に流通、販売をお願いする必要がありました。
ーーパシフィック音楽出版を立ち上げられた1960年代と比較して、現在、日本における洋楽の売上は減少しています。その理由は、なんでしょうか。
朝妻:これは日本に限らず、世界中どこも同じなんですが、まず音楽市場が成長する時というのは、アメリカやイギリスの音楽の影響を大きく受けます。日本もアメリカのモダンフォークから影響を受けて日本語の歌詞のフォークが生まれましたし、グループサウンズもヴェンチャーズやアストロノウツをはじめとするアメリカの音楽の影響ですよね。洋楽の影響を受けながら、その国のオリジナリティを加えながら、どんどん新しい曲が生まれる…。この流れは、世界中どこも同じで、日本だけが例外というわけではありません。
ーー日本で、もっと洋楽が聴かれるようになってほしいと思われますか。
朝妻:それよりも、日本の楽曲がもっと海外で聴かれるようになってほしいですね。
ーー海外展開に関しては、御社も1970年代後半から力を入れておられました。
朝妻:そもそも僕がアメリカに音楽出版社を立ち上げた最初の目的は「日本の音楽を海外に発信すること」でした。ですが、なかなかやってみると難しい。今は時代が大きく変わりましたが、当時は日本語の曲を、日本語の歌詞でヒットさせるのは至難の業でした。日本でも、後に作詞家としても活躍される漣健児さん、なかにし礼さん、岩谷時子さんといった方々が、素晴らしい訳詞によって海外の曲が日本でも広がる橋渡しをしてくださいました。そういった訳詞家をアメリカでも探そうとしましたが、これもなかなかハードルが高い。林哲司さんが書いた「If I Have To Go Away」は、イギリスのグループのジグソーが気に入ってくれて、イギリスやアメリカのチャートに入ったかな。他にもMIDEMに行くたびに日本の楽曲を持っていって、海外のアーティストにレコーディングしてもらえないかという努力は、ずいぶんやりましたね。
ーー最近、シティポップがSpotifyのバイラルチャートにもチャートインするなど、海外でも人気が高まっています。ストリーミングが浸透したことによって、日本語詞の楽曲も可能性が出てきているかもしれません。
朝妻:松原みきさんの「真夜中のドア」や、竹内まりやさんの「プラスティック・ラブ」のように、日本の楽曲に対する評価は上がってきているように感じます。他にも、アニメやコスプレなど音楽以外の日本の文化に対する海外の認知度も高まっていますし、我々にとっても追い風が吹いているなと思います。
関連リンク
Interview:礒崎 誠二/高嶋 直子 l Text:高嶋 直子 l Photo:辰巳隆二
Billboardが功績を称えた朝妻氏の「長期的なビジョンと、経済的な知識」
ーーアジア、特に中国での展開については、いかがでしょうか。
朝妻:当社は香港にも子会社を設立していますが、中国はゲームやテレビ番組での楽曲使用が非常に増えています。特に、ゲームでの使用料は大きいですね。テンセントとユニバーサル、ソニーなどの展開などを見ていると、10~20年前の中国との状況とは変わってきているのかなと思っていたのですが、、、、最近になって中国政府がテンセントと音源会社との契約についてクレームをつけているようなので、ちょっとまだ何が起こるか分からないといった感じがあります。
ーー今回、【Billboard international power players】への選出されたもう一つの理由は、「長期的なビジョンと、経済的な知識」に対してでした。
朝妻:2014年からパルス(Check Your Pulse LLC)と業務提携をしたことを評価していただいたのだと思います。パルスは、ケイティ・ペリーのヒット曲などを管理していたので、大手レコード会社からも業務提携の話があったのですが、パルスのメンバーが、「俺たちは、メジャーの力を借りずに事業を成功させたウィンドスェプト(フジテレビとフジパシフィックミュージックが共同出資して設立した音楽出版社)のような会社にしたいんだ」と言い、僕のところにコンタクトがあったんです。
僕は昔から、キャロル・キングやニール・セダカを管理していたアルドン・ミュージックという音楽出版社が大好きで。「ロックンロールの人気は一過性で定着しない」と、どの出版社も思っていた時代に、ドン・カーシュナーという人が、アル・ネヴィンスに声をかけて、ロックに投資をして大成功をした会社です。
一方、パルスの設立メンバーであるスコット・カトラーは、ナタリー・インブルーリアの歌った「トーン」の作曲を手掛けていましたし、ジョシュ・エイブラハムスもミュージシャンでありプロデューサーです。そんな優れた彼らを見て、「これは、アルドン・ミュージックとシチュエーションが同じだ」と思いました。なので、彼らに「僕がアル・ネヴィンスになるから、君らがドン・カーシュナーになってくれよ」と返事をし、投資することを決めました。その後、マルーン5のヒット曲を書いたスターラ―や、デフ・ジャム・レコードの創始者であるリック・ルービンなど、様々な素晴らしい作家やプロデューサーと仕事をすることができました。もともと「ウィンドスェプトが一つの目標だ」と言ってくれていたパルス自体が、「ある程度、力のあるインディーズと一緒にやりたい」と思っている作家やアーティストにとって、魅力的な存在になっていって。どんどん広げていくことができました。
ーーパルスの設立も含めて、これまで様々な方から提案があり、取捨選択をされてきたと思います。その場合の判断の材料となるのは、その方がこれまでに作ってこられた楽曲なのでしょうか。
朝妻:これまで作られた楽曲が、すごく面白かったり新しいところがあるからこそ、「この才能と一緒に仕事をしよう」と思うわけですが、もう一つ重要なのは人です。やはり、どんな仕事も「誰と一緒にやるのか」というのが一番大切です。ウィンドスェプトを立ち上げた際に、声をかけたチャック・ケイもそんなパートナーの一人です。彼がA&Mの音楽出版社のゼネラルマネージャーをやっていた頃に知り合ったんですが、当時から「優秀な人だな」と感じていました。その頃、当社は洋楽のサブパブリッシャーとしてのビジネスを中心にやっていましたが、だいたいオリジナル・パブリッシャーとの契約というのは、3年で終わることが多いんです。一生懸命に頑張っても、うまくいかなかったら3年で契約は切られるし、うまくいったとしても、その会社が別の会社に買収されてしまって終了することもあって。なのでビジネスをより広げるには「アメリカで、オリジナル・パブリッシャ―として作家と直接契約をする必要があるな」と感じていました。そこで、チャック・ケイに相談したところ、彼から「レコードの制作会社を作ろう」という提案があったんです。シンガーソングライターと契約すれば、必然的に著作権の管理もできるようになるからって。そして、準備をして所属するアーティストも会社の名前も決まっていたんですが、直前で設立できなくなってしまいました。その責任を感じてチャックはA&Mを退職し、その後ゲフェン・ケイという会社を経て、ワーナー音楽出版の会長に就任しました。ですがある時 MIDEMで再会したら、元気がなくて。なので「一緒に音楽出版社を立ち上げよう」と声をかけ、インディーズ・パブリッシャーとしては最も大きい会社にまで成長させることができました。
アメリカの友人からは、「お前は55年も同じ会社にいるのか。1つの会社にずっといるのは、アメリカでは、あまり褒められたことじゃないんだぞ」って言われましたけどね(笑)。でも、そんな彼から「55年も一緒の会社にいるなんて珍しい奴だけど、お前は色んな国の人と仕事をしていて、特にアメリカでもビジネスを成功させられているのは、感心するよ」って言われました。それを言ったのは、シヴィルやソルト・ン・ペパー を輩出したネクストプラトーというレーベルの社長などをやっていた、プロデューサーのエディー・オラウリンです。彼とは70年代の初めにMIDEMで会ったのですが、当時は、MIDEMという場所が音楽業界の見本市であり社交場でもあって、様々な情報交換をすることができました。そこでの出会いも非常にその後の人生に影響を与えています。
ーーここまでのお話を伺って、朝妻さんのキャリアは楽曲の目利きからスタートされ、人との繋がりで広がっていったんだということを実感しました。
朝妻:ニッポン放送で評論家のアルバイトをしていると、毎週ビルボードにチャートインしている楽曲が、レコード室に送られてくるんです。幸いなことに、その曲を全部聴くことができました。そうやって、毎週登場する曲を聴いているうちに「これは日本でも売れそうだな」とか「これは難しそうだな」というのが分かるんですよね。
あとは、ビジネスをする際に「この人とは、長く一緒にできるな」と確信ができるかどうか。そういうバイブスを感じられないと、一緒に仕事はできません。なので幸せなことに、これまで一緒に仕事をした人とは、その後も長く付き合いが続いています。
日本の音楽シーンに期待すること
ーー最後に、これからの日本の音楽シーンにどのようなことを期待されますか。
朝妻:日本以外の収入をどういう風に増やしていくかが、より一層重要になってくると思います。
ーー米ビルボードのHOT100を見ても、BTSを筆頭に韓国のアーティストはチャートインできていますが、日本は坂本九さん以降、大きなヒットは生まれていません。どんなところに課題を感じられますか。
朝妻:まず、大きいのは言葉の問題でしょうね。例えばラジオ番組に出演した時、DJが日本のアーティストに質問すると、通訳がDJの質問を日本語に訳し、アーティストが日本語で答えて、それをまた通訳が英語にしてDJに伝える…。なので、ラジオを聴いている人にとっては、日本語でのやり取りの部分で長いタイムラグが発生してしまうんです。そうすると、チャンネルを変えられてしまいます。
韓国は自国のマーケットが小さかったため、日本やアメリカへ進出する必要がありました。なので、どのアーティストも日本語や英語でのコミュニケーション方法が非常に訓練されており、アメリカのラジオやテレビに出演しても、直接自分の言葉を伝えることができます。日本は幸か不幸か、日本の音楽市場がある程度大きいため、海外へ販路を広げなくても成り立っています。
ですが、コロナによって日本も状況が大きく変わりました。アーティストもマネジメントも、レーベルも音楽出版社も、より海外での展開を念頭に置いて、日本の音楽市場全体を広げていく必要があります。ONE OK ROCKはそういった準備ができているアーティストのうちのひと組なので、アメリカでのヒットに近い場所にいるんじゃないかなと期待しています。
アメリカの音楽市場は、常に新しいことを作り出そうというエネルギーに溢れています。ですので、どういったところが日本では欠けているのか、もっと勉強する必要があると感じています。具体的に何なのかというのは、僕も今は分かりませんが、アメリカではやっているのに、日本ではできていないところが、必ずあると思います。そして、みんなで努力を傾けていけば、絶対に日本の音楽市場のサイズ全体を広げていくことができると思っています。
関連リンク
Interview:礒崎 誠二/高嶋 直子 l Text:高嶋 直子 l Photo:辰巳隆二