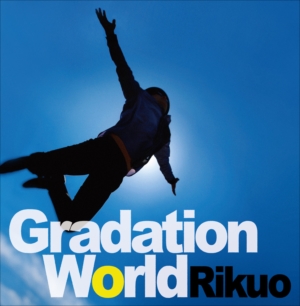Special
リクオ インタビュー:新作アルバム『グラデーション・ワールド』とライブに向けた思いを語る

ツアー! ツアー! ツアー!。年間平均ライブ本数130本(!)を誇る京都出身のシンガー・ソングライター、リクオは、今日もどこかを旅して歌っている。まさにいま現在もウルフルケイスケとの2マン・ツアー、中川敬との2マン・ツアーを並行して行ないながら、弾き語りライブやフェス出演でもあちこち飛び回っている最中だ。それに加えて、リクオwith HOBO HOUSE BANDでの活動がまた絶好調。現メンバー(寺岡信芳、小宮山純平、宮下広輔、高木克)になって結束力が高まり、グルーブの強度がグンと増して、最近のライブはどれも凄まじい盛り上がりを見せている。
そんなリクオがスタジオ録音としては約3年ぶりに発表したニューアルバム『グラデーション・ワールド』は、ライブの熱をそのまま封じ込めたロックミュージックと、洗練された都会的なポップソングの両方が見事な調和力のもとで収められた力作。音楽の持つ昂揚感と幸福感、問いかけとメッセージ、覚悟と希望が共存し、「ポップミュージックを、ロックンロールを、好きでい続けて本当によかった!」と実感させてくれる作品だ。そして、「このアルバム発売からの流れの集大成にしたい」とリクオが意欲を見せるのが、11月5日のビルボードライブ大阪公演と、11月26日の東京・下北沢GARDEN公演。アルバムに参加したゲストの出演もあり、スペシャルな公演となりそうだ。新作とこの公演のこと、そして最近の思いまでを聞いた。
男性客が増えましたね。おっさんの声援が多くなりましたよ、最近(笑)
--7月21日に代々木Zher the ZOOで行なわれた『グラデーション・ワールド』発売記念スペシャルライブ。僕は残念ながら観に行けなかったんですが、アンコールが終わってもお客さんが帰らずに自然と合唱が起きて、ダブルアンコールまでやられたとか。めちゃめちゃ盛り上がったようですね。
リクオ:盛り上がりましたねぇ。BGが鳴ってもアンコールの声が鳴りやまなくて。
--5月の『HOBO CONNECTION』を観ていても感じたことですが、HOBO HOUSE BANDの生み出すグルーブが最近また一段と強力かつしなやかなものになった。それがライブの盛り上がりに直結しているんだなと。
リクオ:そうですね。『グラデーション・ワールド』はプリプロの段階からサウンド・プロデューサーの森(俊之)くんと一緒にがっつりやって、それからバンドのメンバーもスタジオに入って一緒にやるという流れで作ったんですけど、その際、森くんがドラムのこみやん(小宮山純平)とベースの寺さん(寺岡信芳)とペダルスティールの広輔(宮下広輔)にいろいろアドバイスしたんですよ。例えばドラムに関しては、チューニング、ハットの叩き方、リリースタイムまでをアドバイスして。ベースもそう。森くんはリズムに対する意識が非常に高いサウンド・プロデューサーなのでね。で、そのアドバイスがあった上でレコーディングに臨んだので、バンドのグルーブと結束がすごく高まった。
--それが最近のライブにも大きく反映されているということですね。
リクオ:はい。あとは、昨年からギターでかっちゃん(高木克)が参加してくれるようになって、そこから定期的にバンドのライブを積み重ねていったことによって、場ができてきた。お客さんの熱量がライブの度にどんどん高まっていってるんですよ。
--確かにそれは感じますね。“リクオwith HOBO HOUSE BANDのライブは熱い!”という認識がどんどん広まって、それを求めて会場に足を運ぶひとが増えているのを感じます。
リクオ:男性客が増えましたね。おっさんの声援が多くなりましたよ、最近(笑)。
--ロックンロールのノリが強まっているからでしょうかね。
リクオ: 曲の内容が、同じ時代を生きてきたひとたちに訴える力が強くなったからだと思うんです。歌詞だけでなくサウンドも。ある程度自覚的にそういう方向を目指したというのもあるんですけど。
表現の熱量がどんどん高まった
--『グラデーション・ワールド』は確かに以前よりもそこに重点が置かれている印象があります。いま、同世代へのメッセージをこれだけ直截的に言葉にしているアーティストってそんなにいない気がするんですが、リクオさんのなかではその傾向がより強まってますね。
リクオ:逆説的ではあるんですけど、54歳の自分のいまの心情、リアリティを、なるべく正直に表現しようと心掛けることで、同じ時代を生きている世代の近いひとたちに届くようになった。みんなの気持ちを代弁しようというのではなく、もっと自分の思いを赤裸々に伝えようということなんです。そういう姿勢で曲を作って歌うようになってから、より間口の広い伝わり方をするようになった。まずは自分と近い世代に伝わればという思いがあったんですけど、実際アルバムを出してみたら、中学生の子が「オマージュ - ブルーハーツが聴こえる」をかっこいいって言ってくれたりして。“ちゃんとリアリティのあるものを出していけば世代を超えて伝わるんだな”という確信めいたものを得られたところはありますね。
▲ オマージュ - ブルーハーツが聴こえる / リクオ
--ツイッターなどSNSを見ていても、「オマージュ - ブルーハーツが聴こえる」の拡散力は特別なものがあるように感じました。
リクオ:そうですね。今回の作品はキャッチーであるだけじゃなく、パンチラインを効かせることを意識したんです。そこが(前作)『Hello!』との違いですね。刺さる表現をする。サウンド含め、エッジを効かせる。そういうところと、ポップスとして成り立つというところを両立できるように意識しました。森くんとも確認し合いながら、表現として振り切ったものにしようと。
--含ませるというよりは、直截な伝え方。そのこと含めて、ここ2年くらいのリクオさんはロックンロール回帰モードにあるようですが、どうしてもう一度ロックンロールの熱さ、生々しさ、ロマンティックさを信じようという気持ちになっていったんですかね。
リクオ:ひとつは年齢的なものが関係していると思っていて。自分に残された時間を意識するようになった。そうすると、もっと自分に正直になりたいという思いが強くなるんですよ。なんかこう、気持ちの蓋みたいなものがあったとして、50代を迎えるくらいからその蓋がだんだん開いてきたようなところがあって。ネガティブな気持ちも当然持っているわけですけど、そこに蓋をし続けるのではなく開けてしまったほうが、残された人生、より充実したものになるんじゃないかと。それとね、40代の僕はツアーを中心とした暮らしのなかで、楽しむということを最優先していたんですね。音楽を通じて楽しむ術を身につけたと思っているんですよ。だけど50代になったら、今度は楽しいだけじゃ物足りないという思いがでてきた。楽しい以上のことをやりたいというか。
--楽しい以上のこと?
リクオ:前は楽しさで全部埋め尽くそうとしていたところがあったけど、埋め尽くせなくなってきたのかもしれないですね。で、そこを突破していくためには全部ぶっちゃけるしかないなってことで、より正直に自分に向き合った音楽をやっていこうという気持ちが強くなったんです。
--自分より上の世代の先輩ミュージシャンたちが次々に亡くなられたことも……。
リクオ:大きいですね。お世話になった一回り上の諸先輩方の半分以上が亡くなられたんじゃないかという感じなんでね。(高田)渡さんが亡くなったのは56歳だったなとか、(忌野)清志郎さんは58歳で亡くなったなとか。西岡恭蔵さんは50歳で亡くなったから、もう超えてるなとかね。そういうことを思いながら自分に残された時間を自覚して、やり残したことはなんだろうと考えるようになった。そうしたら、いまはとにかく心の蓋を外してやるべきことをやろうというのが大きなモチベーションになっていって、それによって表現の熱量がどんどん高まった。そういうことですね。
--そういうリクオさんの思いがしっかりバンドメンバーたちとも共有されていて、それであの熱さ、あのグルーブが生まれているんだなと感じます。
リクオ:イメージ的には、ブルース・スプリングスティーンとEストリート・バンドに近いかなと思ってます。そう言うと誤解を招くかもしれないけど、自分としてはそんな意識もありますね。で、クラレンス・クレモンズ(サックス)の役割をペタルスティールの広輔がやるという。「永遠のロックンロール」で、Eストリート・バンドならクラレンス・クレモンズが吹くであろうフレーズを、広輔に弾いてもらう。それによってバンドのオリジナリティを出していくということです。HOBO HOUSE BANDのオリジナリティにおいては、広輔のペダルスティールが非常に重要なポジションにあるので。
アルバムを通して、僕のプレイリストを聴いてもらうような意識もある
--なるほど。それから、前作『Hello!』からリクオさんはかつてご自身が影響を受けた作品のオマージュを入れ込むようになりました。あのアルバムには佐野元春さんや上田正樹さんの曲へのオマージュがあった。『グラデーション・ワールド』はRCサクセション、ブルーハーツ、小沢健二さん、ソウル・フラワー・ユニオンなどなど、さらに多くのひとの作品のオマージュをしてますね。そもそもどういったところからオマージュということをしていこうという思いになっていったんですか? 過去にもいまの時代に説得力をもって響くいろんなアーティストの素晴らしい言葉やメロディがあったことを、若い世代にも教えたいというような気持ちから?
リクオ:教えたいと言ったらおこがましいですけど、そういう歴史の連続性のなかに自分の音楽が存在するのは確かなことで。インプットしたもの、受け継いだものがあって、アウトプットしているんだということを、わかりやすく表明したいなと。だからアルバムを通して、僕のプレイリストを聴いてもらうような意識もあります。“あの曲、オレも好きだったな”みたいな感じでね。そうやって歴史を共有してもらえたらいいなという思いがあって。それは『Hello!』から強く意識するようになりましたね。
--意識的にやってるわけですよね。
リクオ:そうです。で、今回のアルバムは、例えるならスプリングスティーンとオザケンの両方の影響でできている。僕は前半5曲と後半5曲をレコードで言うところのA面とB面というふうに、意識的に分けているんですよ。A面前半が汗臭いロックならB面前半はアーバンで洗練されたイメージ。ひとつの作品のなかでそうやって汗臭いものと洗練されたもの、スプリングスティーンからの影響とオザケンからの影響が両立してある作品って、僕の知る限りほかにない。それを一緒にできるというのが僕の音楽性の個性だと思っていて、このアルバムでそのへんが伝わるといいなぁと。
--小沢健二さんの音楽がリクオさんにそこまで影響を与えていたというのは少し意外でした。
リクオ:フリッパーズ・ギターが出てきたときには関西人としては受け入れ難いものもあったんですけど、時間を経て彼らの音楽を素直に受け入れるようになった。彼らによって引用のコラージュという表現方法が広く認知されるようになったわけですが、僕はそういう時代を経ていまの時代を生きている。例えばフリッパーズとピチカート・ファイブを聴かなければロジャー・ニコルズの存在も知らなかっただろうし、渋谷系というムーブメントを通じて僕はより豊かな音楽と出会うことができたわけだし。ただ、フリッパーズを始め渋谷系の音楽は、引用したひとのパーソナリティに対しては距離を置いていて、あくまでも素材として使っていたと思うんですが、僕がオマージュするのは、その音楽を表現しているひとのパーソナリティに親しみを感じているものばかりで。素材として使うという距離感とは違うんですよ。
--人柄こみでもってくる。
リクオ:そう。そのひとに対する思いがあってのオマージュなので。
--それがとりわけ明快かつ濃く出ているのは、やはり「オマージュ - ブルーハーツが聴こえる」ですね。何しろRCの曲に対するオマージュがあり、そこでギターを弾いているのがチャボさんなわけですから。
リクオ:2年前の「HOBO CONNECTION」でチャボさんと竹原ピストルくんと一緒にやるときがあって、この曲はその日までに完成させてチャボさんと一緒に演奏するということを目標に作ったものなんです。そのときから、チャボさんがレコーディングにも参加してギターを弾いてくれることで完結するという意識があった。それが叶って感激しました。
--ギターのフレーズについて、リクオさんのイメージを伝えたりはしたんですか?
リクオ:いや、そんなに細かくはお伝えしてません。イントロはカッティングしてほしいとか、そのぐらいのことですね。
--清志郎さんが「空がまた暗くなる」で歌った「大人だろ、勇気を出せよ」というフレーズにしても、こうしてリクオさんが繰り返し歌うことで、その言葉がいまに甦って力を持つ。いまのリクオさんのリアルなメッセージとして突き刺さる。そこが素晴らしい。
リクオ:10代・20代のときに聴いてきた楽曲が、自分のなかでいまもまったく懐メロになってないんですよね。それは幸せなことだなと思います。だからやっぱり、ロックンロールって問いかけなんだなと、この歳になって改めて思ったりしますね。ピート・タウンゼントが「ロックンロールは悩みから解放してくれる音楽じゃない。ただ悩んだまま躍らせるんだ」と言っていたけど、まさにいま、その言葉が実感として響きます。問いかけ続け、考え続け、悩み続ける。そうさせてくれるのがロックンロールなんだっていう。
--「悩み続ける運命なら ロックンロールで悩もう」(「千の夢」)。あれ、今作のなかでも特に好きなフレーズでした。このアルバムのキーになるフレーズだなと。
リクオ:わかっていてもらえて嬉しいです。
音楽を通じて共感する力みたいなものを育ませてもらった
--ところで、チャボさん始め、有山じゅんじさん、木村充揮さん、亡くなられた(遠藤)ミチロウさんや石田長生さんもそうでしたけど、昔からリクオさんはそうした上の世代の偉大なミュージシャンたちと繋がりを持たれて、一緒にライブをやってきました。それも軽くセッションするといった程度のものじゃなく、そのひとの懐に飛び込んで密な関係を築きながら濃い表現に昇華させるということをしてきた。なかなかいないと思うんですよ、そういうことをこうして積極的にやり続けている50代のミュージシャンって。
リクオ:まあ、そうですね。音楽を通じて、ひとが好きになった気がします。僕は基本的に自分のことばっかりの人間で、こんなに音楽にのめり込む前は他人にあんまり興味がなかった。音楽を通じて共感する力みたいなものを育ませてもらったという気がしますね。
--いつからそういうふうに変わっていったんですか?
リクオ:最初はバンドをやって、バンドの仲間と音を交わし合うことの楽しさ、共通言語を持つことの嬉しさみたいなことを知って。で、ソロでデビューして、メジャーの契約が切れて、お世話になった事務所を離れて、草の根のネットワークを頼りに地方を細かく回るツアー暮らしを始めて。そこからですね。ダイレクトにひとと向きあう機会が急に増えたんですよ。マネージャーもいなくなったので自分で全部ブッキングして、直接、ツアー先でお店のひと、主催のひととお話させてもらって、そのあとの地元の人達との打ち上げにも参加するようになって(笑)
--自分から飛び込んでいかないことには何も始まらないという状況がそうさせた。
リクオ:そうですね。
--気後れすることなく、初めからいけました?
リクオ:僕はラッキーなことに、デビュー前に有山じゅんじさんにツアーに連れていってもらったり、石田さんや憂歌団のみなさんによくしていただいたりして、デビューしてからも上田(正樹)さんと有山さんの地方のツアーを一緒に回らせてもらう機会があったり。そういう草の根ネットワークみたいなものがあるということは知っていて、そういうひとたちが作ってくれた轍を辿ることができたんですよ。
--デビュー前後の頃ということは、年齢的には……。
リクオ:23、24、25の頃ですかね。
--そのくらいの年齢でそういうひとたちとあちこち回るとなると、驚くことも多かったんじゃないですか? こう言うとアレですけど、酒癖のよくない先輩、ややこしい先輩もいらっしゃったでしょうし(笑)
リクオ:楽しかったですよ。予行練習ができたところもあります。そういう経験によってだんだんと音楽を通じてコミュニケートすることの楽しさを覚えていった。ややこしいひとも若い頃からいっぱい見てきたんで(笑)。でも、これは山口冨士夫さんが言ってたことなんですけど、人間のどうしようもないところが出てこないと、そのひとの音楽のよさなんか出てくるわけがないって。
--冨士夫さんとも一緒にやられたことがあるんですか?
リクオ:冨士夫さんとは一緒にやらせてもらったことはないんですけど、僕が学生の頃にファンで、よくライブを観に行っていたんですよ。それで、楽屋に乗り込んでデモテープを渡したことがあって。
--冨士夫さんがTEARDROPSをやられてた頃ですか?
リクオ:そうです。そしたら連絡をいただいて。ちゃんと聴いてくださったようで、「よかったよ」と。で、「ロックンロールは可愛げがないとダメなんだ。清志郎の曲もそうだろ? キミの音楽にもちゃんと可愛げがある」と言ってくれた。それがものすごく自信になったんです。
--それは嬉しいですよね。いい話だなぁ。
リクオ:「人間のどうしようもないところが出てこないと、そのひとの音楽のよさなんか出てくるわけがない」というのは僕に直接言ったんじゃなくて、本に書いてあったことですけど、本当にね、正直さが大事なんだってことはすごく思うんですよね。自分の弱い部分も出しながら、それを含めて正直に相手と接するというか。冨士夫さんはそれを地でいってたような人だったなって。
--ほんとにそうですね。
リクオ:僕が知ってる先輩のひとたち、僕が好きな先輩のひとたちはみんな、どうしようもなさも出しながら、そのなかに正直さ、誠実さといったものが表れていたので。それはオンステージでもオフステージでもね。
--で、リクオさんはそういう上の世代のミュージシャンと自分より若い世代のミュージシャンとを繋ぐ役割も果たしているじゃないですか。「HOBO CONNECTION」がまさにそういうイベントですけど。そういうことをやっぱり楽しんでやられているわけですよね?
リクオ:楽しめるようになったんだと思います、前より。めんどくさいことが好きになったんだと思いますね。ときどき、“なんでオレはこんなめんどくさいことをやってるんだろ?”って、疲れてるときにふと遠くを見ながら思うこともありますけど(笑)。でも結局、そういうことをするのが好きなんですね。
30周年に繋げられるライブにしたい
--さて、11月には5日にビルボードライブ大阪で、26日には東京・下北沢GARDENで、スペシャルライブがあります。
リクオ:アルバム『グラデーション・ワールド』からの流れの集大成にしたいと思っているので、アルバムに参加してくれたメンバーが集結して、あのアルバムの曲は全曲やろうと。
--ゲストも呼んで。
リクオ:はい。大阪は古市コータローくんと、あともうひとり。まだ発表になってないですけど、レコーディングに参加してくれた大先輩が来て下さいます。東京はケーヤン(ウルフルケイスケ)と山口洋も。
--ビルボードライブ大阪でやるのは初めてですか?
リクオ:初めてですね。客としては何度も足を運んでいるんですけど。見やすいし、音もいいですよね。あそこのスタインウェイのグランドピアノが弾けるんだなと思うと、いまから楽しみです。入れ替え制でやるというのも僕にとっては新しいトライですし。特別なステージなので、できれば日本全国から集まってもらえたら嬉しいですね。普段僕がやっているライブハウスに足を運びにくいと感じているひとにも来てもらいたいし、そういうひとたちにも楽しんでもらえる場になればいいなと思ってます。
--わかりました。そういえば来年はCDデビュー30周年だそうですね。もう何か考えているんですか?
リクオ:いろいろやらなきゃいけないなとは思ってるんですけど。まあ、とりあえず11月のライブが30周年に繋げられる形になればいいなと思っているので。楽しみにしていてください。
▲ 永遠のロックンロール / リクオ
関連商品