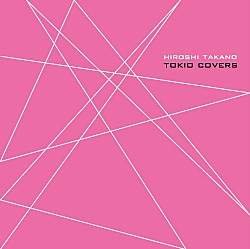Special
高野寛『A-UN』インタビュー

いろんな意味でのアニバーサリーイヤーにしていきたい
宮沢和史とのGANGA ZUMBAインタビュー以来約10年ぶり、30周年直前に氏が体験してきた音楽史と新作『A-UN』について語ってもらいました。高橋幸宏プロデュースでデビュー、トッド・ラングレンのプロデュースでヒット、フリッパーズギターとORIGINAL LOVEとの出逢い、宮沢和史と世界中を駆け巡ったGANGA ZUMBAの功績、忌野清志郎の影響……等々、そんな音楽人生を高野寛が歩んでこれた背景について迫っています。ぜひご覧ください!
YMOやティン・パン・アレーが作った道の上を歩んでいる感覚
--今年10月でいよいよデビュー30周年を迎える訳ですが、自身ではここまでどんな音楽人生を歩んできたなと感じていますか?

高野寛:虹の都へ(Niji no miyako e : 13.12.07 Kyoto Flowing KARASUMA)
--その頃掲げた「理想のミュージシャン像」というのは、具体的に言うとどんなものだったんでしょう?
高野寛:例えば、最初の頃は弾き語りをするにしても集中力が2曲ぐらいしか続かないというか、間がもたなくて。で、ワンステージできるようになったのが90年代の終わり頃からかな? あとは、「描いたイメージをどれだけ演奏とか歌に表せるか?」というところで、思い通りにいかないもどかしさがずっと付き纏っていたんです。でも2000年代に入ってからサウンドプロデュースの仕事だったり、ギタリストの仕事をするようになって、そこで音楽的な基礎体力がグッとついてきて、それが良い感じに自分のソロワークにもフィードバックできるようになってきた。あと、ライブに対する恐怖心が無くなりましたね。--なるほど。
高野寛:それはGANGA ZUMBA(※宮沢和史を中心とした多国籍バンド。日伯交流100周年のタイミングで10,000人規模のフリーコンサートを成功させたり『紅白歌合戦』に出演したりと音楽で幾つもの偉業を成し遂げた)も含めた宮沢くんとの海外での経験が相当モノを言ってる感じですね。--あのプロジェクトでは、宮沢和史や高野寛というアーティストのことを全く知らない人たちの前でライブしまくっていた訳じゃないですか。純然たる音楽の力だけで異国の地で勝負する。
高野寛:その経験はすごく大きかったですね。日本はスタッフが優秀なんですよ。だから日本でツアーするときは本当に手厚いサポートを受けながらやっているんですよね。もちろんファンもいっぱいいるし。だけど、海外では曲も知られていないですし、自分たちで楽器まわりのことをある程度やらなきゃいけなかったり、レンタル機材が壊れているなんてことも日常茶飯事なので、それをどうやって乗り越えるか、そこでいかに慌てないか、ということの連続で。だから「ライブというのはハプニングの連続なんだ」という気持ちで対処できるようになったし、その経験があるから今はツアーで何があってもちょっとやそっとじゃ動揺しなくなりましたね。--あと、冒頭で触れていた「トッド・ラングレンのプロデュースでヒット」という話。当時を知らない人からすると「なんでそんなことが起きたんだろう?」と不思議がると思うんですけど、どういった経緯で実現したものなんですか?
高野寛:僕は一方的にトッド・ラングレンのファンで、1stアルバムのSpecial Thanksのところにトッド・ラングレンの名前を入れていたぐらい影響を受けていたんですね。その直後にトッドのマネージメントから日本のレコード会社に連絡があって「日本のアーティストに興味があるからプロデュースがしてみたい」と。それで「トッド・ラングレンに興味ある人は音源を送ってくれ」という話だったんですけど、ディレクターから「高野くん、送ってみる?」と言われて「もちろんです!」と送ったら、わりとすぐに返事があってプロデュースしてもらうことになったんです。ちなみに、トッドは元々日本びいきなんですよ。家に遊びに行ったら着物が飾ってあるような親日家。で、レコードコレクションもちょっと見せてもらったんだけど、戸川純とかゲルニカとか四人囃子とか……--めちゃくちゃディープ!
高野寛:そういうアーティストのレコードを日本に来る度に買って聴いている、当時としてはかなりコアな日本ファンだったんですよ。だから日本のアーティストに純粋に興味があった。あと、当時は円高で経済的な理由も少なからずあったと思うんです。ただ、そのトッドがいろんなアーティストの音源を聴いた中でチョイスしたのは、僕とレピッシュだけだったというのがトッド・ラングレンらしいし、僕もレピッシュも、トッドがプロデュースしたアルバムがキャリアの中でいちばん売れたアルバムなんですよ。そのマジックというのはトッド・ラングレンならでは。だって、日本ではコアな音楽ファン以外はトッド・ラングレンの名前を知っている人は多くはなかったから、「トッド・ラングレンプロデュース」というキャッチコピーに大きな宣伝効果はなかったはずなんです。それでもヒットしたのは、純粋にトッドの音が説得力を持っていたんだろうなと思う。--そのトッド・ラングレンに限らず、高橋幸宏さんや田島貴男さん、宮沢和史さんをはじめ、高野さんのバイオグラフィーは「出逢いに恵まれて」と仰られていた通り、本当に素晴らしいミュージシャンとの出逢いだらけなんですよね。なんでこんなにも次々と巡り会えたんですかね?
高野寛:うーん……分かりません(笑)。デビューするまでは「自分は運が良い」と思ったことはほとんどないぐらいネガティブ思考だったし、幸宏さんに出逢うまではオーディションも落ちまくっていたので「自分には才能はないんだろうなぁ」と思っていたんですけど……「YMOチルドレン」という言葉があるけれども、YMOは日本の音楽シーンの中で際立った特別な流れを作っているんですよね。やっぱりYMOに影響されてクリエイターになった人たちがミュージシャンに限らず同世代には物凄くたくさんいて、そういう人たちがずっと作っている、今だと「サブカル」と言われちゃうようなところがあるけれども、そういうシーンに自分が飛び込んでいけたので、その流れの中で、YMOやティン・パン・アレーが作った道の上を歩んでいる感覚があって、その中でのいろんな人との出逢いがあってね。とは言え、偶然もすごく大きいです。「なんでそのタイミングでトッド・ラングレンが日本にオファーをくれたのか」とか。僕がデビューする半年ぐらい前に、渋谷のライブハウスでたまたま観ていたイベントにフリッパーズギターとORIGINAL LOVEが出ていて、そこでみんなと知り合いになったりとかね。まだ「渋谷系」という言葉のカケラもない時代で、みんなデビュー前で。今思うとそういう歴史の偶然みたいなモノが幾つかあったんですよね。- 前代未聞のプロジェクト・GANGA ZUMBA「時間が経ってから再評価される可能性」
- Next >
前代未聞のプロジェクト・GANGA ZUMBA「時間が経ってから再評価される可能性」
--今の話、日本の音楽史の流れそのものですもんね。
高野寛:ただ、その渦中に巻き込まれてからは、僕はちょっと波に乗り切れなかったんですよ。それを想定していなかったからね。「自分がヒットしてポップスターになる」みたいなことを全然イメージできてなかったので、とにかく波に飲まれて溺れないようにするのに必死でした。という意味では、1回そういうシーンと距離を置いて、自分のペースで活動するようになってからのほうが、表現はちゃんと地に足がついていて、自分の理想に近づけた気がしますね。--ここ数年で30周年や25周年を迎えたアーティストは他にもたくさんいますが、高野さんみたいな30年の歩み方をした方って他にいないですよね?
高野寛:いないかもしれないですね。1966年生まれの人たちはね、層が厚くて。僕よりふたつ下なんですけど、よく一緒にライブやったりとかしていて、みんなメジャーシーンの第一線を歩み続けている感じなんですけど、僕の場合は元々シンガーになるつもりもなかったんですよね。幸宏さんに「歌ってみれば?」と勧められて歌い始めたようなところがあって。自分はボーカリストだという自覚と同じくらい、ギタリストやサウンドクリエイターという感覚があるから、そこが端から見てちょっと分かりづらいところでもあると思うんです。でも、ソロと並行してギタリストやサウンドプロデューサーとしての活動も続けてきたことで、「1年に1枚は自分のアルバムを出さなきゃいけない」というプレッシャーもなく、ちゃんと納得いく作品が出来たタイミングでリリースすることを続けて来れたので、そういう意味でも自分らしく21世紀に入ってからは活動していくことができたんです。--なるほど。
高野寛:あと、弾き語りのツアーを1998年とか99年ぐらいから始めて……当時はまだ全然流行ってなかったんですよ。今みたいにみんながアコースティックで廻るような時代ではなかったから「なんで弾き語りでやってんの?」って不思議がられるぐらいだったんですけど、そこでひとりで廻れる基礎体力をつけられたのは大きかったし、そのあとに宮沢くんたちと世界を廻ったり、いろんな方のサウンドプロデュースをしながらスタジオワークのバージョンアップをしていったりとか、そういう積み重ねが大きかったですね。同時期に自分でプロトゥールスを買って、ちゃんとCDの音源に出来るクオリティで録音できるようになってきたり、タイミングがちょうど良かったんですよね。この十年ほどでみんなが始めたことをわりと早い時期から出来ていたので。--そうした道を歩まれたこともあって、高野さんはザッツ・ミュージシャンだなと思うんですよね。高野さんが「渦中に巻き込まれてから、1回そういうシーンと距離を置いた」時期って今振り返ると実態よりイメージでモノが売れていく時代じゃないですか。でも高野さんはイメージより実態を重要視して音楽と対峙していたんじゃないかなって。
高野寛:そうですね。やっぱり「良い曲を作りたい」というモチベーションがいつも自分の中で一番強い。僕はハンドマイクだとあんまり上手く歌えないから、ステージではギターを持っていたいし、フロントに立ったとしても、エンターテイナーとして強くアピールはできるわけじゃない。だからこそ、自分がやるべきことは良い楽曲を作り続けることなんじゃないかなと思う。そういうタイプのアーティストの作品をいっぱい聴いて、ずっとそうやって活動してきて。音楽バカですね(笑)。--それゆえに様々なプロジェクトに関われたところはありますよね。それこそエンターテイナーとして「高野寛たるものこうでなきゃいけない」みたいなイメージに縛られるような活動を選ばなかったからこそGANGA ZUMBAもあったと思いますし、音楽に対してフットワークが軽くあれる状況を自分で作ってきたからこそ、この30年があったとも言えるというか。
高野寛:それも、先輩方の影響だと思うんですよ。トッド・ラングレンもプロデューサーであり、シンガーソングライターであり、時にはコンピューターグラフィックのアーティストだったりもするんですよ。細野晴臣さんもそうですよね。僕はYMOにもはっぴいえんどにもティン・パン・アレーにも影響を受けているんですけど、よくよく考えてみるとはっぴいえんどとYMOに同じメンバーが居るって物凄いことじゃないですか。意味が分かんないですよね(笑)。でもそうやって万華鏡のようにスタイルを変えながら、同時にアーティストでもありプロデューサーでもあり、今もNever Young BeachやYogee New Wavesみたいにはっぴいえんどをリスペクトする若者が出てきているぐらい、オリジネーターとして時代を超える作品を作り続けている。僕はずっとリスペクトし続けていますね。--個人的には、GANGA ZUMBAも後世に語り継がれていくべき伝説的ユニットだと捉えているんですが、日本とブラジルのより良い交流を願いながら音楽活動してきた存在なんて僕は他に知りませんでしたし、そういう意味ではマイノリティではあったとは思うんですけど、そのプロジェクトが日伯交流100周年のタイミングで『紅白歌合戦』に出演するまでの見事な完成を遂げる。後にも先にも見たことのないストーリーでしたよね?
高野寛:たしかにそうですね。そこまで持って行った原動力は、宮沢くん自身のブラジルに対する愛だったと思います。彼が最初にブラジルに行ったのは90年代半ばぐらいだったはずだから、そこから20年以上の年月の結果だったので……僕はメンバーだったけど、同じ船に乗っている乗組員というだけで、牽引力、エンジンは宮沢くんでしたね。本当に良い経験をさせてもらったと思ってます。ただ、今でも残念なのは、あの頃はSNSが今ほど普及していなかったので、海外で活動していたりしてもごく一部の人にしか情報が伝わらなくて、もしあの頃インスタでもあったら……かなり話題になっていたんじゃないかなと思うんです。とは言え、リーマンショック前だから出来たことだとも思うので。リーマンショック後というのは、なかなかあんな風に大きなプロジェクトで海外に行くことが難しくなってきたので、そう考えると時代の必然だったのかもしれない。あと、GANGA ZUMBA周辺を追いかけて下さっていた方はこうやってずっと憶えてくれているだろうし、もしかしたらもう少し時間が経ってから再評価される可能性もあるかもしれないと思っています。--高野さんにとって、宮沢さんはどんな存在だったりするんですか?
高野寛:GANGA ZUMBA以前から長い付き合いですし、宮沢くんとはすごく近しい友達でもあるんだけど、言葉にする必要がないお互いへの理解みたいなモノがすごくあって。あと、宮沢くんもYMOの影響を受けている世代なんです。だから宮沢くんが海外で成功するイメージはYMOが影響を与えていると思うんですよね。そんなことを本人からも聞いた気がするんだけど……そもそも「島唄」という曲を生み出して、これだけ沖縄の音楽だったり三線という楽器をポピュラーにしたっていう、その功績だけでも90年代のロック史の中ではかなり大きい出来事だったと思うんです。それはもっともっと評価されていいことだと思うし、それに加えてブラジルにも目を向けて、ブラジルのミュージシャンとの交流も深めて、レコーディングやツアーにも何度も何度も行っていて。僕みたいに個人的な目線で「ただ良い音楽を作る」というモチベーションではなくて、宮沢くんはいつも社会にコミットしていく動きをしてきたと思うんですよね。それが彼のロックだし、凄いところだと思う。忌野清志郎の影響「「デイドリームビリーバー」の訳詞は原曲よりも素敵」
--3月14日の高野寛×宮沢和史×おおはた雄一@ビルボードライブ東京も楽しみなのですが、その前に高野さんは『A-UN』(あ・うん)なる新アルバムをリリース。自身ではどんな作品になったと感じていますか?
高野寛:本気の大人の遊びですね。セルフカバー中心のアルバムなんですけど、これは佐橋佳幸(Darjeeling)さんのアイデアで。普段の僕がプロデュースしているソロアルバムとちょっと雰囲気を変えてみようということで、自分でも忘れかけていたようないろんな提供曲があって、その中からDarjeeling(ダージリン)のおふたり(Dr.kyOn&佐橋佳幸)に選曲して頂いたんです。--自身の提供曲を実際にセルフカバーしてみてどんなことを感じました?
高野寛:自分が歌うつもりで作っていない楽曲なので、例えば田島くんとの共作曲(「Affair」)でも田島くんが作ったパートに関しては「うーん、この歌詞! うん、田島貴男!」と思いながら(笑)、ちょっと前だったら抵抗感があったと思うぐらいエロい歌詞なんですけど、それを「これも面白いじゃん」と歌えるようになったのは、大人の遊びなのかな。--例えば、矢野顕子さんへの提供曲「ME AND MY SEA OTTER」も矢野さんをイメージして作られている訳で、矢野さんと高野さんは全然タイプの違うアーティストだしシンガーですから、それを自分の歌にするというのは相当なチャレンジですよね。
高野寛:本当にその通りで。だから「セルフカバー」というか、ほぼ「カバー」ですよ(笑)。コード拾うところから始めたりして。全然忘れてるんですよ。歌詞もコードもゼロからおさらいして、体に馴染ませて、今の自分が無理なく歌えるように「キーはどのへんがいいかな?」と探ったり、本当にカバーするのと同じ感覚でやっていた感じです。女性ボーカルの曲だったり、自分だったら普段歌わないようなスタイルの曲だったりするので、普段のソロよりもだいぶ難しかったですね。やっぱり再解釈が必要になるから、そこはDarjeelingとプリプロをして、イメージの擦り合わせをしていって、リズムの骨組みをバッサリ変えてみたり、細かいコードも結構変えていったし……普段だったら「歌詞をどう書くか、どういう言葉を使うか」みたいなことですごく悩んだりもするんだけど、今回は曲自体はすでにある訳だから、それをどう料理するかというところに徹して、どう仕上げてどう食べるか?みたいな。いつもとは全然違いましたね。--また、今作には、ボブ・ディラン「時代は変わる」の日本語訳カバーが収録されています。この曲を訳して歌おうと思った経緯はどんなものだったんでしょう?
高野寛:何年か前に、国会前デモで中川五郎さんがこの曲の日本語カバーを歌っている動画を目にしたんですよ。それは高石ともやさんというフォークシンガーの方の訳詞で、ほぼ直訳だったんですね。その内容があまりにその時の状況と重なっていたんで、ちょっとビックリして興味を持ったんです。ただ、直訳なので言葉のハマり具合みたいなものが字余りっぽいというか、まぁそれが昔のフォークの特徴なんですけど、それを自分なりにもうちょっと自分の歌として置き換えられるかなと思って作り始めたんですね。その後も1年間ぐらいライブで歌い続けて、少しずつ言葉を変えていったり、トランプ大統領の誕生などの世の中の動きも反映して、完成させた曲ですね。--高野さんはザッツ・ミュージシャンでありながら、こういうメッセンジャーとしての側面も時折見せるじゃないですか。この「時代は変わる」はまさにそういう曲だと思うんですけど。
高野寛:それは忌野清志郎さんの影響ですね。元々RCサクセションは好きだったんだけど、僕がデビューしたときに偶然RCと同じディレクターが担当だったんです。その時期はRCがちょうど『COVERS』をリリースするときで、だから発売中止騒動の一連の動きをいちばん身近なところで見ていて、そのあとタイマーズが結成されたりするんですけど、僕もキヨシローさんのイベントによく誘ってもらったり、観に行ったら飛び入りで参加させてもらったりしていて、晩年は家が近所だったんで録音の手伝いもしたりしてました。普段はとても優しい人でね。僕の日本語ロックのお手本ですし、キヨシローさんは「歌詞カードがなくても歌詞がぜんぶ聴き取れるように歌い方をすごく研究した」と仰っていたり、言葉のアクセントとメロディーをなるべく一致させる詞の載せ方とか、そういういろんなところで影響を受けていて。--なるほど。
高野寛:あと『COVERS』に代表される洋楽の日本語カバーのセンスがすごく好きで、僕は「デイドリームビリーバー」の訳詞は原曲よりも素敵だなと思うんですよ。完全な直訳ではないけど、曲の雰囲気とか大きな意味合いを損なわないで、日本のポップスの名曲になっている。だから若い人がセブンイレブンのCMでしかあの曲を知らずにモンキーズのオリジナルを聴くと「あれ? これ何? 英語のカバー?」と反応するらしいんですよね。もっと若い世代になると、あれをキヨシローさんの曲とも知らずに「セブンイレブンのテーマ」だと思っているかもしれないけど(笑)。そんなキヨシローさんの言葉の強さや、メッセージにはすごく影響を受けていますね。--「歌詞カードがなくても歌詞が聴き取れる」これは今作収録のオリジナル新曲「みじかい歌」にも反映されていると思うのですが、胸にじんわり染み渡る人間味溢れるナンバーとなっています。どんな想いを込めて書かれたんですか?
高野寛:40過ぎた頃から「自分の人生、折り返しに差し掛かったなぁ」と感じるようになって、近しい人が亡くなる機会も多くなるし、そういう中で生まれた曲だったと思うんですけど、この曲も書いたのは結構前なんですよ。自分の中で“新曲”の概念が曖昧になってきていて、ライブでずっとやり続けて、身体に馴染んでから録音することが多いので、新曲と言いながら、実は結構古い。10年ぐらい前からあった気がする。そういう曲で「10年後の自分を思い描いても」と歌っているのはなかなか意味深ですよね(笑)。--10月には30周年を迎える訳ですが、どんなアニバーサリーイヤーにしたいと思っていますか?
高野寛:もちろん今までを振り返るベスト盤も出すと思いますし、総括したライブとかもやりたいんですけど、もっといろいろ意外な展開を見せたいですね。ただ過去を振り返って「バンザーイ」で終わりたくはない。この『A-UN』も新しいことに挑戦していますけど、そういう新しいこと、そんな次に繋がっていくようなことを見せられたら、良い30周年になるんじゃないかなと思っています。あとは、縁のある人たちとの共演をフィーチャーしたライブもやってみたいですね。やりたいアイデアはたくさんあるけど、いくつ実現出来るか(笑)。でも30周年は老人になる前にバリバリに動ける貴重な機会だと思うし、来年は年号も変わるということなので、いろんな意味でのアニバーサリーイヤーにしていきたいなと思っています。関連商品