2018/01/22 18:00
ポーランドの指揮者、スタニスワフ・スクロヴァチェフスキは、2017年2月に惜しまれつつその生涯を閉じた。2005年から常任指揮者、2010年から桂冠名誉指揮者も務めた読売日本交響楽団との縁は30年以上にわたり、ライブを数多くこなしたことは記憶に新しいが、今回発売された3つのアルバムは、いずれもNHK交響楽団とのライブ録音だ。
その内訳は、2002年のモーツァルトの第35番、36番『ハフナー』に2006年のブルックナーの第8番を併せたもの、2002年に録音された、ブルックナー第4と第9の入ったアルバム、そして2004年録音のベートーヴェンの交響曲第3番、第4番、第7番にフィデリオ、コリオランとエグモント各序曲をカップリングしたもの。いずれも2枚組で、都合6枚ものN響とのライブ録音がまだ残っていたことをまずは喜びたい。今回は、そのなかからベートーヴェン盤について見てゆきたい。
スクロヴァチェフスキは、この録音の直後、2005年から翌年にかけてザールブリュッケン放送響とのベートーヴェン全曲録音を開始しており(OHEMS)、2012年以降の読響との録音もある(DENON)。いずれも音楽の構造が透かし彫りになるようなスクロヴァチェフスキの特質は共通している。それにしても熱気に満ちた演奏ばかりだ。『英雄』は、いきなり各々の音符は水を得た魚のように踊り飛びはね、第1楽章展開部にコーダなど、あらゆる音に意味があると信じたスクロヴァチェフスキが志向したサウンドの解像度は極めて高く、さりとて情感に欠けた機械的印象を与えることもない凜としたエネルギーが横溢している。高らかなこの『英雄』を耳にするだに、1923年生まれだから録音当時80歳を超えていたわけだが、老いてなお、というより、老いてより一層瑞々しい演奏を展開した指揮者であることを再確認した。
第4番も、第1楽章から音はベッタリとした音の塊にならず、刻み一つ一つの襞、各楽器の息づかいまで聞こえてくる。第2楽章で、情感豊かに旋律をたっぷり歌わせつつ、時折感に堪えないようにくぐもった声を発しているのもご愛敬。最終楽章はタイトな快速テンポで刻み、展開部から再現部にかけての装飾的フィギュレーションを活写したあと、コーダの締めの前には思いきりアゴーギクを効かせてメリハリをつけている。
第7番でもN響はマエストロのタクトによく反応している。序奏以降は付点リズムで押し通す第1楽章のみならず、全楽章で偏執的、と言っていいほどに繰り返す同一リズムがキモとなるこの曲で、明快にリズムパターンを切り出す。最終楽章はこのアルバム最大の聞き物の一つで、N響を煽って駆け抜けるが、潰れも掠れもしないN響のアンサンブル能力は流石。オスティナートも唸りをあげる弦セクションの分厚い音響は、スケールの大きな燃焼度高い白熱の演奏を生み出し、終演するやいなや聴衆から喝采が飛ぶのもむべなるかな。スクロヴァチェフスキの妙技と魅力とが詰めこまれたディスクである。Text:川田朔也
◎リリース情報
スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ(指揮)NHK交響楽団
『ベートーヴェン:交響曲第3、第4、第7番』
ALT385/6
関連記事
最新News
関連商品


アクセスランキング
インタビュー・タイムマシン

グローバルにおける日本の音楽の現在地






注目の画像



 ヒラリー・ハーン・ベスト 過去と現在を繋ぐ回顧展(Album Review)
ヒラリー・ハーン・ベスト 過去と現在を繋ぐ回顧展(Album Review)  新国立劇場2018/2019シーズンラインアップ発表 次期オペラ芸術監督に大野和士
新国立劇場2018/2019シーズンラインアップ発表 次期オペラ芸術監督に大野和士 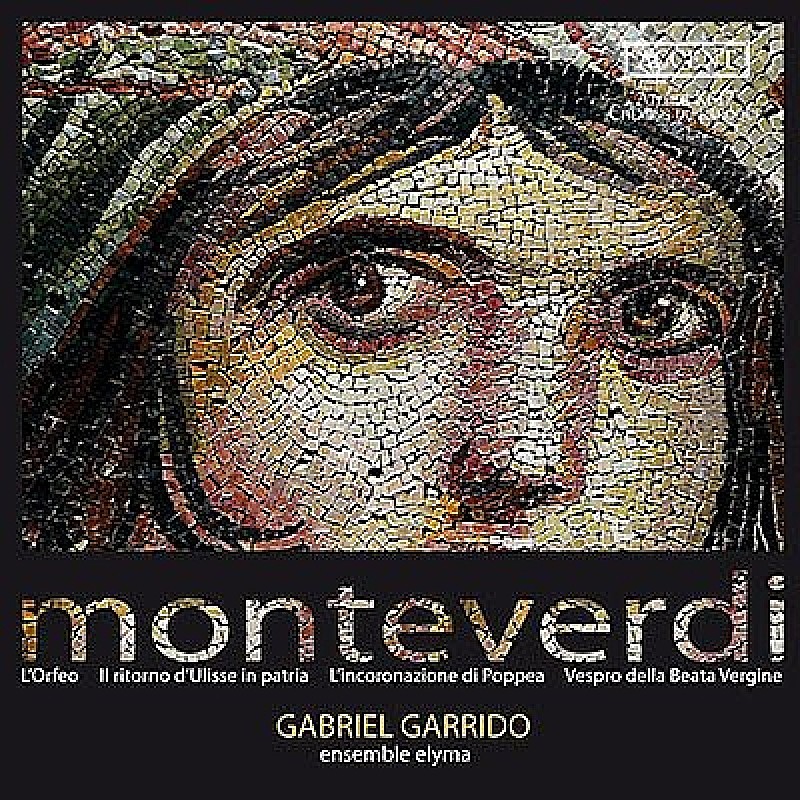 2017年のクラシック・リリースを振り返る、インディペンデントが再評価進む
2017年のクラシック・リリースを振り返る、インディペンデントが再評価進む  1848年製のプレイエルで弾く、小倉貴久子のビゼー(Album Review)
1848年製のプレイエルで弾く、小倉貴久子のビゼー(Album Review) 










