2022/08/23 21:00
ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作する日本最大級の音楽フェスティバル【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】(以下【RIJF】)が、千葉市蘇我スポーツ公園にて8月6日、7日、11日、12日の4日間にわたり開催された。(※13日は台風接近により開催中止)
2020年および2021年は、新型コロナウイルス流行の影響でやむを得ず中止となった【RIJF】。今年は開催地を茨城県ひたちなかから千葉県蘇我に移し、できる限りの感染対策をすることで3年ぶりの開催に至った。会場では入場時の検温をはじめ、食べ物を持ち込めるエリアの制限や、スタッフによるマスク着用の声かけ、客席の前方エリアは事前抽選にしてディスタンスを確保するなど、さまざまな感染対策が行われた。
記念すべき1日目、メインの<GRASS STAGE>でトップバッターを務めたのは、5月にグループ結成14周年を迎えた週末ヒロイン、ももいろクローバーZ。【RIJF】では総合プロデューサーの渋谷陽一氏による開幕宣言がお馴染みの風物詩だが、この日「スタートには彼女たちしかいない!」と紹介された4人は、そのお墨付きに応えるべく、グループの代名詞的なキラー・チューン「行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-」で開演。いつもならファンの熱烈な掛け声や歓声でも盛り上がるこの曲でも、間奏部分では代わりにコール&レスポンスならぬコール&ジャンプを煽ったりしていて、様々なリアクションが制限されるこの状況下のパフォーマンスをしっかり心得ている様子。以降も、百田夏菜子が自己紹介パートをアレンジして「みなさん、誰を見にきたんですか? バンドですか? フェス飯もいいですよね?……ももクロ降臨!!」と高らかに宣言した「ダンシングタンク」、衣装の早替えでも魅せた「ロードショー」とショーは加速、加熱の一途をたどっていく。
サウンド面で4人を支えるのは大所帯のDMB(ダウンタウンももクロバンド)で、ホーン・セクションの涼し気なインタールードからなだれ込んだのは、踊れるサマー・ソングの決定版「ココナツ」。タオル旋風がフィールドを埋め尽くした「ツヨクツヨク」、その景色が突き上がる拳に変わった「孤独の中で鳴るBeatっ!」を経て、ラストはブラス・ロックの高揚感で“Make Some Noise”できずとも“Free Your Soul”してみせる「サラバ、愛しき悲しみたちよ」へ。最初から最後まで全力ダッシュで駆け抜けたバイタリティ、オーディエンスの心を鷲掴みにするアイドルとしての愛嬌、そして常に“新しいももクロの姿”を提示し続けてきた楽曲のバラエティ、15周年という大きな区切りを目前としたグループの、第一線で積み上げ続けた経験値が存分に生かされた快演だった。
ラインナップの多様性が色濃い1日目の【RIJF】。前述のももクロや、DJを除けば<GRASS STAGE>のトリになる[Alexandros]のように、コロナ禍以前からアリーナやスタジアムを沸かせまくっていたアクトもいれば、若手期間のブレイクスルーに少なからずパンデミックの逆風を受けつつも、サブスク世代のリスナー、デジタル・ネイティブ層を中心に支持を拡げてポピュラリティを確立してきた緑黄色社会、Vaundyなどもいる。
『Early Noise 2020』に選ばれたあたりから頭角を現し始めたVaundyはロッキン初出演ながら、野外フェスの開放感、一体感をばっちり味方につけたアクトを見せてくれた。セットリストはストリーミング再生回数が億超えの楽曲もふんだんに交えた、とにかくヒット曲、定番曲のオンパレードで攻めまくる濃縮構成で、客層入り混じるフィールドのニュートラルな温度感は楽曲を重ねていくたびに熱を帯びていく。一方で、あっけらかんとした表情でぼそぼそと「ちょっと疲れたな」「みんな元気だね」「俺も気合入れないと」とオーディエンスに喋りかけるVaundy。その大胆不敵な雰囲気、ロック・スター然とした佇まいもライブでこそ見られる彼の一面だし、それこそラスト・スパートは、ファンの熱視線もグレー層の好奇心も高みの見物勢も、すべてひっくるめてクライマックスに連れていくアンセムの連打で、これぞロック・フェスの醍醐味といった光景を生み出していた。
対岸の<LOTUS STAGE>では、Saucy Dogが登場。ちょうど1年前、2021年8月にリリースしたアルバム『レイジーサンデー』に収録された「シンデレラボーイ」がロング・ヒット中の彼らも新世代シーンの旗手だ。ショーは涼し気な風を吹かせるサマー・チューン「シーグラス」で始まり、石原慎也(Vo./Gt.)の歌声がどこまでも伸びていきそうな「シンデレラボーイ」や「いつか」といったミドル・バラードの名曲も押さえつつ、煌びやかなメロディを撒き散らしながら疾走する「雀ノ欠伸」を筆頭に、シンプルかつボーカル・オリエンテッドな3ピース・バンドの強みを体現した楽曲で、これまた夏フェスのオープンな空気感と相性抜群。
一方の<HILLSIDE STADE>に登場した、東京出身の“エキゾチックロックバンド”を標榜するNEEは、どこかライブハウス的な密室感、そこに生まれる共謀感覚をむしろ野外でどこまで拡張できるかというパフォーマンスで、バンドの野心的なアティチュードを覗き見たアクトだった。その拡張感覚は続く羊文学も同様で、普段なら淡いドリーム・ポップ、内省的で繊細なインディー・ロックの音像が室内で反響を繰り返し、徐々に陶酔へと引き込んでいくヒプノティックな演奏も、この日は<PARK STAGE>の丘を見晴らせる広大な空間に挑むダイナミズムを宿していて、改めてこのバンドの高いポテンシャルを露呈する格好に。綺麗な三角形を描く3人の立ち位置も、まさしくフィールドに向かって音を放出するパラボラ・アンテナのようだったし、バンドが最新アルバム『our hope』で獲得した、より肉体的かつ開けたメジャー志向のサウンドが本領を発揮した瞬間でもあったと思う。
直情的なロック・チューン「インフェルノ」で勢いよくスタートしたMrs. GREEN APPLEのステージには、2020年夏にベスト・アルバムをリリースし、それまでの歩みにひと区切りつける形で完結したフェーズ1と、この春に幕を開けた新体制でのフェーズ2、二つの時代の上に跨って立つバンドの凛々しく、堂々たる姿があった。「ロマンチシズム」「StaRt」とフェーズ1楽曲を続けて披露していった前半戦では、そうした往年の楽曲が過去として色褪せることなく、むしろポジティブな再構築の気概に満ち満ちていたのが印象的だったのだ。
【RIJF】の出演は彼らも3年ぶり。「ただいまー!」と挨拶するミセスのパフォーマンスを久しぶりに見て、そのヘアカラーと衣装以上に鮮やかさを増した楽曲群、そして3人のステージングに驚きを感じたオーディエンスも多かったのではないか。「WHOO WHOO WHOO」もド直球のEDMを鳴らすナンバーではあるが、かといってありがちなピーク・タイムではなく、前半戦から後半戦に移る鮮烈なインタールードとして演奏されていて、このバンドの音楽性がいかに全方向へ振り切れているか、どこまでも自由なポップネスを証明する一撃だったし、その多彩なレパートリーを証明するように、ステージ上の彼らも実に鮮やかなモード・チェンジを次々と決めていく。
そこまでの空気をガラッと変える壮大なバラード「僕のこと」を経て、「フェーズ2はじまりの曲です」と紹介されたのは、新たな時代の到来を告げるハピネスを纏った「ニュー・マイ・ノーマル」で、続く「ダンスホール」では客席から巻き起こった特大クラップ、大森の華麗なステップも祝祭感に拍車をかけた一幕に。その勢いのままゴールテープを駆け抜けた「青と夏」はフェスティバルとミセス、両者のエンターテインメントが幸せな合致を極めたクライマックスの清々しいフィナーレだった。
現行の音楽シーンを大いに盛り上げるアーティストたちが揃った今年の【RIJF】初日、ヘッドライナーとして<LOTUS STAGE>のトリを務めたのは、小説を音楽にするユニット、YOASOBIだ。本来なら昨年の【RIJF】で有観客ライブ・デビューするはずだった彼ら、そして、数日前のフジロックも残念ながら出演キャンセルとなった彼らにとって初めての夏フェスとなったこの日のステージは、そうした雪辱を晴らすリベンジであったと同時に、Ayaseが過去のインタビューで話した「フェスで勝つライブ・バンド」という、YOASOBIの2022年以降の目標に対して、最初のマイルストーンになるアクトでもあった。
ステージ上にさらにスクリーン一体型の特設ステージを組み立てたセットは、映像を駆使するYOASOBIのプロダクションを完全反映。お馴染みのバンド・メンバー(ただし、ギターはAssHの代打で田口悟(RED in BLUE))ががっちりかみ合い、屈強なアンサンブルを構築するストイックな演奏と、イマジネーションの喚起力に溢れたikuraの繊細な歌声が合わさり、音と光の圧倒的な情報量がオーディエンスをまるっと包み込むスケール感も、昨年末の日本武道館ワンマンで最初に感じた彼らのライブ・パフォーマンスの真髄だ。
オープナーの「夜に駆ける」は、まさしくYOASOBIのシグネチャーとなるサウンド、歌、世界観を叩きつける決定打的な露払いで、客席からも「待ってました!」と言わんばかりにどよめきが上がる。トライバルなビートとikuraのラップ・ライクなボーカルがキレキレの「三原色」や、音のレイヤーが幾重にも重なる「大正浪漫」などは、明らかにライブ・パフォーマンスのハードルが高いナンバーだが、バンド・マスターとしてのAyaseがしっかり交通整理をして、もしくは今年から刷新された【RIJF】のサウンド・システムの影響もあってか、ずいぶんとクリアな状態で音が届いていた印象だ。
また、『めざましテレビ』のテーマ・ソングにも起用された「もう少しだけ」では、ikuraと映像内の世界がシンクロするような演出も。「ハルジオン」を歌い終えたあとの煽りで若干甘噛み気味だった彼女だが、そんな気取らない人間性の魅力と、曲が始まれば何かが憑依したかのように世界観に没入していく表現者としての佇まい、それらのギャップも含め、YOASOBIが愛される所以がとことん詰まった約1時間のショーだったと思う。
アンドロイド、人間、心、感情といったキーワードで描かれた『私だけの所有者』(著:島本理生)を原作とした「ミスター」、どこか儀式めいた演出も神秘的だった「もしも命が描けたら」、スマホのライトが客席に星空を作り出した「アンコール」の3曲は、退廃的でシリアスな世界観の流れで、悲壮感と哀愁がボーカルにもより一層こもる。物語の語り部としてのikuraが、その瞬間、ステージ上で実際に存在する登場人物=幾田りらとして歌を届ける、その複雑な表現者としてのアプローチは、YOASOBIのライブを唯一無二の体験にしている要素のひとつだ。
そう、YOASOBIが「フェスで勝つライブ・バンド」を目指すうえで導き出したファイティング・ポーズとは、ロック・バンドに擬態したポップ・ユニットでもなければ、わかりやすく他のアクトと差別化する異色の存在でもない。ただただYOASOBIがYOASOBIを100%、いや120%やりきる、そういう類のモードだった。和の旋律がひたすらキャッチ―な「ツバメ」を皮切りにした後半戦、軽やかなシンセ・ポップ「好きだ」、一転してダークなデジロックになだれ込む「怪物」と動的なショー運びを経て、改めてプレイリスト時代的な楽曲の幅広さをアピールしつつ、最後の「ラブレター」と「群青」で生まれた大団円の光景は、彼らの大勝利を何より饒舌に物語っていた。
Photo:ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022
◎イベント情報
【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】
千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
8月6日(土)7日(日)11日(木・祝)12日(金)
※13日(土)は台風接近により開催中止
<セットリスト>
■Saucy Dog
01. シーグラス
02. メトロノウム
03. シンデレラボーイ
04. 雀ノ欠伸
05. ゴーストバスター
06. 優しさに溢れた世界で
07. いつか
08. Be yourself
■Mrs. GREEN APPLE
01. インフェルノ
02. ロマンチシズム
03. StaRt
04. WHOO WHOO WHOO
05. 僕のこと
06. ニュー・マイ・ノーマル
07. ダンスホール
08. 青と夏
■YOASOBI
01. 夜に駆ける
02. 三原色
03. ハルジオン
04. 大正浪漫
05. もう少しだけ
06. ミスター
07. もしも命が描けたら
08. アンコール
09. ツバメ
10. 好きだ
11. 怪物
12. ラブレター
13. 群青
関連記事
最新News
関連商品


アクセスランキング
インタビュー・タイムマシン


グローバルにおける日本の音楽の現在地




注目の画像







 King Gnu/あいみょん/miletら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】2日目まとめレポ
King Gnu/あいみょん/miletら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】2日目まとめレポ  バンプ/優里/Awichら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】3日目まとめレポ
バンプ/優里/Awichら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】3日目まとめレポ  UVERworld/ワンオク/BE:FIRSTら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】4日目まとめレポ
UVERworld/ワンオク/BE:FIRSTら出演 【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022】4日目まとめレポ 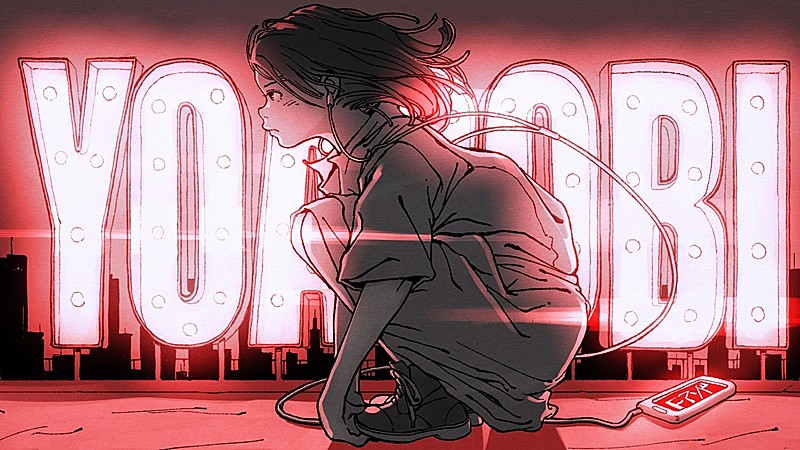 YOASOBI、日本武道館有観客ライブ映像3曲を3日連続YouTube公開決定
YOASOBI、日本武道館有観客ライブ映像3曲を3日連続YouTube公開決定 Mrs. GREEN APPLE、二宮和也/北川景子/中島健人ら出演の映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌を担当
Mrs. GREEN APPLE、二宮和也/北川景子/中島健人ら出演の映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌を担当










